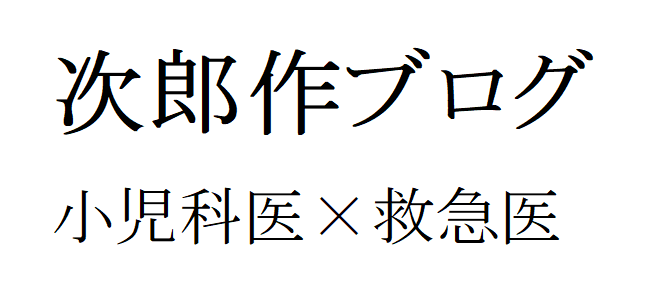目次
1. 【外傷初期診療のprimary/secondary survey】
2. 【外傷と蘇生】
3. 【外傷性心停止】
4. 【外傷と感染症】
5. 【外傷と呼吸管理】
6. 【外傷とドレーン管理】
7. 【腹部コンパートメント症候群 ACS】
8. 【外傷と凝固線溶異常】
その他の巻についてもこちらをご覧ください↓
——————————————————————–
【1.外傷初期診療のprimary/secondary survey】
・基本はABCDEの順にアプローチ
・A(airway), B(breath), C(circulation)を安定させればPTD(preventable trauma death)が発生する確率が低くなる
・ABCを安定させた後に、D(dysfunction of CNS), E(exposure and environmental control, 脱衣による体表観察と体温管理)を行う。
・primary surveyの前に、声掛けで反応を見たうえで上肢に損傷がなければ橈骨動脈の触診を行う。これだけで意識レベル・自発呼吸の有無・顔色(ショックの有無)・主訴・麻痺・抹消循環動態をチェックできる。
・ABCの診察をしながら
・酸素10L/min(リザーバーマスク)の投与
・モニター類の装着
・末梢血と動脈血の採血
・2本の静脈路確保
・出血性ショックの際には輸血指示
を行う。
[気道確保]
・頸部気管損傷、喉頭損傷、気道系の出血は気道閉塞をきたすことがある。
・気道を確保しなければ、患者はすぐに死ぬ。
・気道閉塞は、
・声が出せない
・陥没呼吸
・努力性呼吸
などをもとに判断
・気道閉塞の場合には、迷わず経口気管挿管を選択
(ただし、気胸の場合には陽圧換気は禁忌)
・口腔内の大量出血などで挿管困難な場合には、輪状甲状靱帯穿刺/切開を行う
[呼吸]
・視診、聴診、打診、触診の五感を利用した診察が基本となる。
・胸部だけでなく、頸部の視診により頚静脈怒張(閉塞性ショック:緊張性気胸、心タンポナーデ)、触診により気管変位や皮下気腫(緊張性気胸)などを診察する。
・身体診察とともに、胸部X線の撮影を行う。
・胸部エコーにより、心タンポナーデの有無を確認する。
[呼吸の異常を呈する胸部外傷]
・緊張性気胸
・開放性気胸
・フレイルチェスト
・肺挫傷
・気管/気管支損傷
・大量血胸
・外傷性横隔膜破裂
[循環]
a.触診
→皮膚の冷感がないか、橈骨動脈が触れるかどうか(sBP 80mmHg)、頻脈かどうか
→ CRT2秒以上であれば末梢循環不全
・収縮期血圧は循環血液量の約20%以上の出血で低下し始める
・収縮期血圧90mmHgであればショック状態である。
b.出血性ショックの診断
・体幹内での大量出血の部位のほとんどが胸部・腹腔内・後腹膜腔(骨盤腔内)
・胸部と後腹膜腔はX線写真から、腹腔内はFAST所見から診断する
(FAST:http://www.iryokagaku.co.jp/frame/03-honwosagasu/393/393_90-93.pdf)
・外出血については、圧迫止血などを行う
(追記:止血には①圧迫②結紮③焼灼の三種類があるが、動脈性の出血であっても心臓より高い位置で適切に圧迫を加えれば、止血できることが多い)
c.循環の異常をきたす胸部外傷
・心タンポナーデ
・緊張性気胸
・大量血胸
・大動脈損傷
・心筋損傷
・大量血胸、大動脈損傷
→出血性ショック
・心タンポナーデ、緊張性気胸
→閉塞性ショック
・心筋挫傷
→心原性ショック
[追記:外傷性出血に大量輸液はNG]
(www.nishiizu.gr.jp/intro/conference/h30/conference-30_02.pdf)
・外傷に大量輸液を行うと、生体外由来のミトコンドリア破壊産物(DAMPs)が全身に拡散され炎症、凝固障害を起こす。
・生体にとっては細菌感染も外傷も似たようなものということになります。
・出血性ショックから死亡までのmedian time(中央値)は2時間。
・患部に対しては、局所圧迫が有効でなければ止血帯が推奨される。
・駆血帯の上、輸液制限し即座に病院搬送、sBP80-90、最終処置まで輸液控えよ!
・ultrarapid “scoop and run concept” : 警察が駆血帯して病院搬送。
・出血性ショックから死亡までの中央値は2時間!
・最終的止血処置まで輸液を控えることは生存率を改善!
・病院前治療は意識と橈骨脈拍を保つ(sBP80)少量の生食・乳酸リンゲルの投与!
・最初の6時間内の晶質液輸液は3ℓ以内に留めよ!
・輸血は全血または赤血球:血小板:血漿は1:1:1。
[緊張性気胸]
・身体所見で診断する
(胸痛・呼吸苦・頸動脈怒張・患側呼吸音の低下・皮下気腫・気管偏位など)
・胸部X線による確定診断で治療開始を遅らせてはいけない
・ただちに胸腔穿刺(第二肋間鎖骨中線上に16G以上の穿刺針)、あるいは胸腔ドレナージ(第五肋間中腋窩線上に28Fr以上)
[心タンポナーデ]
・FAST施行時に診断する
・その他、Beckの3徴(頚静脈怒張、血圧低下、心音減弱)など
・診断がついたら、出来れば心嚢穿刺し15-20mLのドレナージでバイタルサインは改善する
[切迫するD]
・ABCの安定が得られた後に行う
→そうでないと、意識障害が過大評価される可能性がある
・生命を脅かす中枢神経障害のことを指し以下の徴候が出現する
・GCS8 (JCS30)以下
・GCS2点以上の急速な悪化
・瞳孔不同、片麻痺、cushing現象(呼吸抑制、血圧上昇、徐脈)
・切迫するDがあれば、primary survey終了時に頭部CTを撮影する。
・頭蓋内占拠性病変は緊急手術を考慮する。
[secondary survey]
・切迫するDがなければ問診から
S:Symptom(主訴、症状と随伴症状)
A:Allergy
M:medication(治療薬)
P:Past history & Pregnancy
L:Last meal
E:Event & Environment
・情報収集の後は、全身をくまなく診察
a. 頭部・顔面
・頭蓋低骨折を示唆する眼窩周囲の皮下血腫がないかどうか
・眼窩、口鼻腔、外耳道などから出血、髄液漏がないかどうか
・頭髪被覆部に創傷がないかどうか
・陥没骨折がないかどうか
・上顎/下顎の咬合不全がないかどうか
(追記)
・眼窩底骨折による複視や、頬骨骨折による眼窩下神経障害(胸部・歯茎の知覚障害)に着目する
・顔面骨の骨折は基本的に緊急疾患ではない
→機能/整容的問題による整復手術は骨繊維の癒合が始まる2週間以内に行えばよい
→緊急性があるのは、眼窩底骨折に下直筋絞扼(複視・嘔気が強い)
・明らかな機能障害・神経障害がなく、本人も気にしない場合には形成外科受診は不要
b. 頸部
・頸椎棘突起の圧痛の有無を確認
・四肢のしびれ、麻痺、呼吸困難を確認
・頸椎カラー離脱の基準は以下をすべて満たすこと
・頸椎/頚髄損傷の正確な所見がとれること
(意識障害や薬物の影響がないことなど)
・自覚所見/他覚所見/神経所見がないこと
・損傷を疑う受賞基点がないこと
・頸椎運動時痛がないこと
c. 胸部・腹部・骨盤・四肢
・胸部の触診は、胸骨中央を押す→両側胸郭を圧迫→肋骨一本一本
・腹部ではFASTを必ず実施する
・生殖器、会陰、肛門の診察で陰嚢付近の皮下血腫や外尿道出血を確認
・直腸診で直腸損傷、後部尿道損傷を確認。直腸の連続性がなければ腹膜炎を疑わなければならない。
・四肢は変形、主張、外傷痕、擦過傷、開放創の有無、圧痛部位、間接内血腫の有無を確認
[tertiary survey]
・主たる損傷の治療終了時や入院経過観察中に、隠れた損傷を探し出す診察「tertiary survey」が繰り返し必要となる。
・外傷初期診療のsecondary survey終了時に重要なことは、検索した損傷に対する根本治療の必要性を判断して、専門医に依頼すること。
・自己の能力を超える場合には、適切な診療科の医師に引き継ぐ、転院を含めて検討する
・自施設で対応するのであれば、根本治療や経過観察の中でtertiary surveyを繰り返し行う
[ICUでの創傷管理の要点]
a. 軟部組織の開放創
・筋膜を超える深さ、高度の汚染、広範囲の組織欠損を認めるものは手術室で適切な麻酔下にて、洗浄と徹底的なデブリードマンを行う。
・汚染が高度な創、受傷後6時間以上経過した創は縫合せず開放創とする。
・感染の危険性がなくなった時点で閉創する。
・抗菌薬の予防的投与として、受傷後4時間以内、かつ洗浄やデブリの前にGPC感受性の抗菌薬を投与する。
b. 四肢の骨折
・骨折がある際は、骨折部から末梢の色調・冷感・動脈触知の有無と左右差を観察し、変形・血行障害・神経障害の発生に注意する。
・開放骨折には予防的に抗菌薬投与を行う。
→第三骨片を伴う場合や広範な軟部組織損傷を伴う場合にはGNRもカバーする広域抗菌薬を投与
・コンパートメント症候群は前腕・下腿骨の骨折後や血行再建後に発生する。腫脹・疼痛のあとに知覚異常・運動障害が出現する。筋区画内圧45mmHgで筋膜切開による減圧を行う。
——————————————————————–
【2.外傷と蘇生】
[外傷蘇生のポイント]
・心肺停止時の蘇生とは異なり、”外傷による侵襲を受けた患者に対する輸液・輸血を中心とした治療行為”を指す。
・ショックの原因として、当然出血が圧倒的に多い。
・止血後緊急再開腹の適応としては
① 正常体温にも関わらず4単位/hrの出血が持続
② 出血が持続している腹部コンパートメント症候群
[死の三徴]
a. アシドーシス
・外傷患者においては、出血による循環不全→嫌気性代謝亢進→乳酸産生亢進により代謝性アシドーシスの状態に陥りやすい。
・アシドーシスの治療で重要なのは「pHを補正するのではなく、アシドーシスの原因を治療する」こと
・見逃されやすい原因として、後腹膜臓器(十二指腸・膵臓)の見逃し損傷や腹部コンパートメント症候群が挙げられる。
・生理食塩水大量輸液による高塩素血症(AG正常)も忘れてはならない。
→(追記)ただし、上述のように、外傷に対する大量輸液は推奨されない
b. 低体温
・外傷患者の低体温は予後不良因子
・外傷患者はすぐに低体温に陥るため、体温低下の予防及び保温措置を念頭に置く
・輸液は加温したものを投与する。
c. 凝固異常
・外傷患者の凝固異常はさまざまな因子が複雑に関与している。
・因子としては
・大量輸液・赤血球輸血による凝固因子希釈
・低体温・アシドーシスによる凝固因子。血小板の活性低下
→(追記)
・外傷に大量輸液を行うと、生体外由来のミトコンドリア破壊産物(DAMPs)が全身に拡散され炎症、凝固障害を起こす。
・最初の6時間内の晶質液輸液は3ℓ以内に留めよ!
・輸血は全血または赤血球:血小板:血漿は1:1:1
[適切な蘇生法とは]
・従来の、低体温とアシドーシス予防に重点を置いた蘇生法から、凝固異常予防にも重きを置いた蘇生法へ
→重症外傷例における凝固異常は、受傷直後から存在しており、積極的な補正が死の三徴への進行を防ぐカギである
・晶質液の大量輸液の弊害を鑑み、sBP90mmHgを目標とするpermissive hypotensionと新鮮凍結血漿の高比率投与の有効性が考えられる
[外傷蘇生のゴール]
・バイタルサインや尿量の安定が得られても、組織への酸素の供給が十分であるとは言えない。
・ゴールドスタンダードはない
・(追記)急性期の蘇生が終わったら、乳酸値、BE を確認する。これらの正常化は蘇生が順調であり新たな出血はないことを示唆する。
(http://www.nishiizu.gr.jp/intro/conference/h30/conference-30_02.pdf)
[輸液・輸液療法の選択]
・ICUにおける輸液蘇生時の、生理食塩水 vs 4%アルブミンは死亡率、臓器障害の頻度に有意差なし
・外傷患者に限ったサブグループ解析では、アルブミン投与群で死亡率が高い傾向にあった。ただし有意差はなし
→現時点で積極的な膠質液の投与は推奨されない
・(追記)
外傷で出血するとアドレナリンにより毛細血管が収縮し組織が低酸素となり破壊されます。これに大量輸液すると、心筋梗塞時の tPA 投与による再灌流みたいにischemia-reperfusion injury が起こり、オキシダント、サイトカイン、炎症仲介物が 大量に全身に環流し臓器障害、炎症、免疫抑制を起こすと言うのです。
また大量輸液は腹部、四肢のコンパートメント症候群、炎症、ARDS、多臓器障害を起こします。また大量輸液で凝固因子が希釈され凝固障害も起こします。
晶質液(crystalloid:生食、乳酸リンゲル)の輸液過剰により酸素運搬能低下、 凝固因子濃度の低下が起こります。また輸液で低温になると熱、エネルギーが失われます。
酸性晶質液(生食の Ph4.5-8.0、乳酸リンゲル Ph6.0-7.5)の過剰で低還流による酸性度は更に悪化し、凝固因子阻害、悪循環(vicious cycle)の凝固障害、低体温、酸性となります。
なお蘇生にアルブミン、高張食塩水、高張デキストランの使用は生理食塩水に比べて 利点はありません。
(http://www.nishiizu.gr.jp/intro/conference/h30/conference-30_02.pdf)
[輸血開始のタイミング]
・JATECでは2Lの輸液に反応しない場合に輸血を考慮
・活動性出血のない患者の輸血開始タイミングとしてHb 7mg/dl以下と10mg/dl以下では予後に差がない
・ただし急性期の出血に対しては、輸血を制限することで大量輸液につながり、腹部コンパートメント症候群のリスクが高まるのでは。
[大量輸血療法の合併症]
大量輸血の定義は「24時間以内に赤血球10単位 or 循環血液量に相当する量の輸血」とされている
・近年、輸血関連急性肺障害(TRALI)が注目されている。
→輸血後の呼吸不全の鑑別として重要。輸血後6時間以内に発症する。
→ICUにて輸血を受けた8%が発症し、FFP・PLTの輸血でリスクが高い。
→原因は
① 同種抗原抗体反応
② 非特異的免疫反応
③ 輸血関連免疫寛容による易感染状態
④ 肺胞内毛細血管の透過性亢進状態における体液過剰
などが挙げられる。
[非手術療法]
・非手術療法(血管内治療と保存的加療)の適応基準は
① 患者の循環動態が安定していること
② 腹膜炎の所見が認められないこと
③ 手術が必要な損傷が存在しないこと
・循環動態、腹部所見、貧血進行の有無を確認しながら、所見の増悪が見られた際には緊急開腹術が必要となる。
——————————————————————–
【3.外傷性心停止】
・Traumatic CPAの全体の生存率は2.2%で神経学的障害を残さないものはわずか0.8%
・鈍的外傷によるTCPAは穿通性外傷によるものと比べて予後が悪い
・蘇生行為には、緊急開胸による心マッサージ・大動脈遮断術や心膜穿刺/開窓術などもふくまれる
[蘇生行為の適応]
・内因性の心肺停止である可能性がある
・溺水、電撃外傷、低体温症例
<蘇生を行わない、もしくは中止を考える>
・鈍的外傷による心停止で、現場で呼吸・脈がなく心電図上も電気的活動がない
・発見時に呼吸・脈のない穿通性外傷例で、さらに対光反射、自発活動なし、心電図上も電気的活動がない
・首切断や下半身切断
・紫斑や腐敗があり、死後長時間経過している
・心肺停止確認後、搬送までに15分以上かかっている
・現場で心肺停止が確認され、15分以上心肺蘇生に反応しない
(米国救急医学会作成)
→日本では、到着までの時間の上限が20-60分と幅があり、統一されていない。
→蘇生に反応しない時間の上限も30分が一番多く、米国よりも長い
救急室開胸の適応
a. 鈍的外傷
・施設到着後に心停止となった症例
b. 穿通性心損傷
・施設到着後に心停止となった症例
・5分以内の院外CPR後の搬送、かつ到着時に二次的なバイタルサインを認めた症例
c. 心損傷を伴わない穿通性胸部外傷
・施設到着後に心停止となった症例
・15分以内の院外CPR後の藩王、かつ搬送時に二次的なバイタルサインを認めた症例
d. 腹部血管損傷
・施設到着後に心停止となった症例
・施設到着の際に二次的なバイタルサインを認め、かつ腹部血管損傷の根本的修復が可能な症例
——————————————————————–
【4.外傷と感染症】
[頭蓋低骨折と髄膜炎予防]
・頭蓋底の骨折では髄液漏の有無に関わらず、ルーチンの抗菌薬投与は必要ない
・一般的に推奨されている予防的抗菌薬はない
[チェストチューブ挿入中の感染予防]
・チェストチューブ挿入時には十分な清潔操作を心掛ける
・チェストチューブ挿入中の抗菌薬についてはいまだ結論はない
・抗菌薬を投与する場合は投与期間を挿入前から24時間とする。
・基本的には黄ブ菌(MRSAもふくめて)をカバーできればよい
[穿通性腹部外傷における予防的抗菌薬投与]
・穿通性腹部外傷では、できるだけ早く予防的抗菌薬の投与を開始する
・複数を組み合わせる必要はないが、嫌気性まで広くカバーする
・管腔臓器の損傷があり、手術による修復ができた場合には初回投与から24時間で終了とする。管腔臓器の損傷がない場合には術前のみでよい。
[開放骨折に対する予防的抗菌薬投与]
・開放骨折での予防的抗菌薬投与は受傷後できるだけ早く開始する。
・GPCをターゲットとしたセフェム系でよいが、第三骨片を伴う場合や広範な軟部組織損傷を伴う場合にはGNRもカバーする広域抗菌薬を投与
——————————————————————–
【5.外傷と呼吸管理】
[確実な気道確保のアルゴリズム]

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsca/32/2/32_2_191/_pdf
[迅速気管挿管(Rapid Sequence Induction)]
・前酸素化
迅速導入では患者の意識消失から気管挿管終了までの時間を短縮するため、静脈麻酔薬と筋弛緩薬は間をおかず投与される。この一連の流れによっても無呼吸の時間は30秒程度になると考えらえる。喉頭展開や気管挿管に手間取った場合、無呼吸の時間は容易に60-90秒を超える。この間、動脈血酸素分圧を安全な範囲に保つためには、麻酔導入前の酸素化が重要な意味を持つ。3-5分の通常換気量あるいは、それには劣るが1分間に8回の深呼吸による酸素化で挿管に備える。
筋弛緩薬非投与下でも、レミフェンタニルとプロポフォールを使えば挿管は可能だが、嗄声や声帯のびらんなどの合併症を引き起こすリスクが高くなることから、筋弛緩薬投与可能な状況であれば、使用が推奨される。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsca/28/4/28_4_590/_pdf/-char/ja

http://www.med.nihon-u.ac.jp/department/eccm/study/2014/mawatari_20140623.pdf

http://anesth.or.jp/63rd/file/R03_sap.pdf
[肋骨骨折]
・肋骨骨折は肺挫傷・血胸・大動脈損傷などを合併する
・折れた肋骨の本数と死亡率に相関が認められる。
・肋骨骨折患者の死亡率は10%であり、肺炎・ARDS・気胸・誤嚥性肺炎などの合併率が、本数が多くなるにしたがって増加する。
・治療は鎮痛と保存的加療
→保存的加療には、適応があればNPPVによる換気も含まれる。
[フレイルチェスト]
・連続する2本以上の肋骨が2カ所以上で骨折している場合、連続した肋骨骨折に胸骨骨折や肋軟骨骨折を伴うものをいう。肺挫傷、血胸を合併する
→鎮痛のうえ、陽圧換気や観血的整復固定を行う。
[鎮静と鎮痛]
・疼痛に対して適切な鎮痛薬を用い、過不足なく鎮痛を行うことは極めて重要である。
・疼痛により咳嗽を抑制し、無気肺の形成が起こりうる。
・外傷後の疼痛に対して、鎮痛が十分でないとPTSDのリスクが高くなる
・ICUでの鎮痛は十分ではことが多く、オピオイドを積極的につかっていく
[肺炎]
・VAP(Ventilator Associated Pneumonia)は挿管患者の9-27%で出現
・入院期間を7-9日延長する
・ただし、外傷/ARDS患者ではVAPが死亡率に寄与する部分は大きくない
・外傷の中でも、重度の頭部/頸部外傷がVAP発症リスク
[脂肪塞栓症候群]
・時間経過に伴って増悪する意識障害でかつ、頭部CTで血腫・脳挫傷がない場合に疑う
・骨折後の骨髄から脂肪成分が血中に流入し、二次的な経過により小動脈を塞栓する
・頭部MRIで多発梗塞巣を認める。
[神経原性肺水腫]
・頭部外傷後の急激な酸素化低下で疑う
・原因ははっきりとわかっておらず、一般的な支持療法を続けながら、原疾患のコントロールが出来れば、48-72時間で軽快する。
——————————————————————–
【6.外傷とドレーン管理】
[胸腔ドレーン管理]
・第4 or 5肋間腋窩中線から肺尖部に向けて、背側に28Fr以上を留置。
・陰圧は-10~15cmH2O
・陽圧換気中の気胸に対するドレナージは、効果が不十分だと緊張性気胸になるため注意
・ドレーンの排液性状・排液量・排気量を確認
・気胸のドレーン抜去目安は
① 肺が完全に膨張している
② 吸引や咳をしてもエアリークがない
③ クランプ(4-6hr)後に気胸の再発がないことを確認する
[血胸]
① 血液をドレナージ
② 出血量をモニタリング
③ 同時に気胸に対するドレナージも行う
④ 肺が膨張すると出血部位を塞ぐことで止血効果が得られる。
→排液が100~200mL/day以下で抜去
→1000mL程度のドレナージ量を目安に開胸止血
[膿胸]
・肺挫傷、ドレーンの長期留置がリスクとなる。
・抗菌薬の予防投与に利益はない
乳び胸
・胸管の損傷に伴い乳びが胸腔内に漏出・貯留した状態である。
・胸部手術の術後合併症として生じることが多い
・白濁した胸水が特徴的で、持続的な漏出は栄養状態の悪化や電解質異常、免疫異常を起こす。
・ドレーンは陰圧をかけずに水封とする。200mL/day以下で抜去。
・保存的加療中は絶食でTPN
[腹腔ドレーン]
・ドレーン留置の目的と位置
① ダグラス窩:術後出血や縫合不全の有無の確認
② 横隔膜下:貯留液排除
③ 傍結腸溝:術後出血や縫合不全の有無の確認
④ winslow孔:胆管吻合後の胆汁漏や胃吻合後の縫合不全やドレナージ目的
[腹腔内出血/損傷の診断]
・排液の性状だけで確認することは難しい
・バイタルサインや輸液・輸血の必要性、アシドーシスや貧血の進行などを総合的に判断する。
・腸管穿孔や膵損傷があるときは、腹水AMYが上昇する。
・腸管/胆道系損傷では腹水Bilは血清Bilよりも高い時に疑う。
[腹腔内感染/膿瘍]
・感染徴候とともに排液に濁りが生じた場合には、排液のグラム染色を行う
→10,000個/mL以上細菌が存在するときにグラム染色陽性となり、腸管穿孔や吻合不全、膿瘍形成が疑われる。
→培養も提出し、抗菌薬の感受性を確認する。
——————————————————————–
【7.腹部コンパートメント症候群 ACS】
・ACSは大量出血を伴う重症外傷において合併する
・ACSを合併すると死亡率は40%にも達するため、腹腔内圧の上昇にいち早く対応することが求められる。
[定義]
a. 腹腔内圧(IAP)
→正常値はやや陰圧からゼロ
b. 腹腔内圧上昇(IAH)
→4-6時間の間隔をあけた3回以上の測定でIAPが12mmHg以上に上昇している状態
c. IAHの重症度分類
Ⅰ 12-15
Ⅱ 16-20
Ⅲ 21-25
Ⅳ >25
d. 腹部コンパートメント症候群(ACS)
持続的なIAPの上昇(>20mmHg)を認めるなかで尿量減少やP/F<200以下の呼吸不全を合併している状態。またこれが減圧処置により改善するものをいう。
[primary ACS]
・腹部外傷に伴う容量増加が原因となるものをいう
・DCの導入により、大量出血による死亡例は少なくなったが、一方でパッキングガーゼや術後の腹腔内出血などの影響によりIAH/ACSが増えた。
・初回手術の後は、IAPが上昇しやすいことや、手術時間を短縮する目的からopen abdomenとなることが多いが、それはかならずしもIAH/ACSを予防しない
DC:大量出血を伴う外傷患者に対して、迅速な止血と腹腔内の汚染回避のみに主眼をおいた初回手術と生理学的異常の改善、そしてその後の根本治療の3ステップからなる。
大量出血に伴う外傷患者に合併する低体温・凝固異常・アシドーシスの死の三徴を改善するための治療戦略。
実際には、ガーゼパッキングなどによる迅速かつ可及的な止血ののちに、ICUでの代謝補正に引き継ぎ、改善の後に根本治療を行う。
[secondary ACS]
・他部位の出血に対する大量輸液を行った結果生じるACSを指す
(→繰り返しだが、外傷に伴う大量出血に対して大量輸液が有害)
・敗血症に対する大量輸液を行った後のACSも含む
(→EGDTの大量輸液は近年CareBundleにとって代わった)
AKIの『1.病態』を参照
[各臓器に与える影響]
a. 心血管系
・全身血管・肺血管抵抗の増加とともに、心拍出量の低下を起こす
・血管抵抗の上昇による左室後負荷の増加により、一回拍出量が低下する。
・肺血管抵抗の上昇による右室後負荷の増加により、右心不全傾向となる。
→CVPとPAWPは上昇する
b. 呼吸器系
・IAPの上昇に伴い、横隔膜が押し上げられ胸腔内圧が上昇する。
・気道内圧の上昇、肺コンプライアンスの低下などから分時換気量が減少し、酸素化障害及び換気障害が出現する。
c. 腎尿路系
・IAPの上昇に伴う心拍出量の減少と全身血管抵抗の上昇により腎血管抵抗も上昇、腎機能障害を引き起こす。
・IAPの上昇によりカテコラミン分泌の亢進、RAS系の亢進により腎血管が収縮し悪循環に陥る
d. 中枢神経系
・頭蓋内圧が上昇する
・上記のカテコラミン/RAS系の亢進は本来、脳血流を保つためのものだが、心拍出量がさらに減少すると、代償機構が破綻し著しい中枢神経系の血流減少に至る
e. 肝・消化器系
・IAPが10mmHg以上になると、肝・腸管血流の減少を認める。
・血流低下がbacterial translocationを引き起こし、腹腔内感染・多臓器障害の原因となる。
f. 四肢末梢系
大腿動脈の血流が65%減少する。
[腹腔内圧の間接的測定法]
・膀胱内圧
→膀胱内圧=腹腔内圧と考えてよい
→頭部挙上では実際よりも高い状態にある。
・実際の膀胱内圧測定方法
① バルーンカテーテルを挿入
② 膀胱内の尿を完全に排除
③ 生食25mL程度を注入したあとに採尿ポートよりも遠位部でクランプ
④ クランプを一度解除し、回路内のエアーを排除した後に再クランプ
⑤ A lineなどの圧波形モニターを18G注射針につなげて採尿ポートを穿刺して測定
⑥ 測定時のゼロ点は中腋窩線に
[ACSの循環血漿量管理]
・腹部灌流圧(APP)
→平均動脈圧(MAP)-IAP=APP
→膀胱内圧を持続的にモニタリングすることで、APPも持続的に見ることができ、APPを50~60mmHgで管理することが望ましい
・ACS/IAHのリスクとなることから、大量輸液は避ける
・アルブミンなどの膠質液の有用性は否定的である。
[ACSの非手術療法]
a. 体位
・頭部挙上でIAPが上昇するが、挿管されている患者の場合、VAP予防のために頭部挙上されていることが多い
・バランスを見ながら体位を検討する。
b. 鎮静・鎮痛
・疼痛やストレス、興奮は胸腹部筋の収縮からIAPを上昇させる
・鎮静や鎮痛はACSの対抗策となる
c. 筋弛緩
・IAPを有意に低下させるが、VAPのリスクとなる
・DCの初回手術でopen abdomenとしている場合は筋弛緩が不可欠
d. その他
・腸管運動の低下によるガス貯留がIAHにつながる
・胃や腸内容物のドレナージや腸蠕動亢進薬が有効
・利尿剤による腸管浮腫の軽減がIAPを低下させる
・減圧開腹が困難な場合には、腹腔穿刺によるドレナージでIAPを低下させることが出来る。
——————————————————————–
【8.外傷と凝固線溶異常】
・外傷に伴う凝固線溶反応は①生理的反応と②病的反応(DIC)に分けて考えることができる
[外傷後の生理的凝固線溶反応]
① 組織損傷とそれに伴う血管内皮損傷が凝固系の活性化が生じ、フィブリン形成が行われる
② 過剰なフィブリン血栓による血管閉塞を防ぐために、二次線溶が起こりD-Dimerが上昇する。受傷後短時間で始まる。
③ 二次線溶亢進の持続により、再出血のリスクが高まるため、プラスミノーゲン活性化インヒビター(PAI-1)の発現が増加する。D-dimerは低下する。受傷後24時間程度でこの線溶遮断が起き長いと7日間継続する
④ 損傷血管内皮や組織の修復が終わると、フィブリン血栓が不要となり、これを溶解するためにPAI-1の活性が低下し、線溶系の再活性化が起きる。D-dimerが再上昇する。
[DIC]
・DICに至った症例では、上記生理的線溶反応に対して、線溶亢進が著明となる。凝固亢進は同程度である。
・臓器障害が出現することはまれであることから、出血のコントロールによりショックから脱することが出来れば、凝固線溶異常から離脱可能である。
・大量輸液による凝固因子の希釈や、低体温・アシドーシスにより凝固反応の抑制が起きる
・外傷急性期の凝固異常には末梢循環不全が強く関与している。
[重症外傷における静脈血栓塞栓症]
・重症外傷において静脈血栓塞栓症のリスクは40-80%と高い
・予防なしでは、50%がDVTを発症する
・脊髄損傷、下肢骨盤骨折、大腿静脈カテーテルの挿入などがリスク因子
・下肢痛がすでにあるor訴えるこができないなどの理由から、疑うことが困難となる。
[予防法の比較]
a. 間欠的空気圧迫法
・下肢骨折非合併例においては間欠的空気圧迫法が有用とする試験と、そうでないとする試験がある
→予防効果について、統一された意見はないが、出血のリスクが高く抗凝固療法が行えない患者へは有用性が期待される
b. 抗凝固療法
① すべての重症外傷例に対して、静脈血栓症の予防を可能な限りルーチンに施行する。

② 禁忌となる状態がなければ、可能な限り早期から低分子ヘパリンを投与する
(追記):出血が未分画群で有意に多いデータが一部あるが、現状低分子ヘパリンが明らかに優れているというデータはなく、値段などの観点からも未分画ヘパリン(ふつうのやつ)の投与でよい

(http://www.jseptic.com/journal/30.pdf)
③ 活動性出血の存在、あるいは出血のリスクが高い時は間欠的空気圧迫法や男性ストッキングを使用する
④ 予防目的の下大静脈フィルターは推奨されない
⑤ 全例にエコー検査をする必要はない
⑥ 重症外傷に対しては、退院まで予防を行うことを推奨する。リハ中もヘパリンor ワルファリン(INR 2.0~3.0)投与を継続する。
川良健二
その他の巻についてもこちらをご覧ください↓