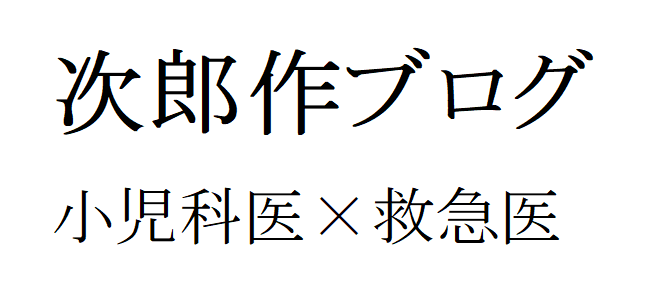目次
1. 【体液動態】
2. 【輸液製剤の各論】
3. 【輸液必要性と反応性】
4. 【septic shockに対する輸液療法のまとめ】
5. 【急性呼吸不全の輸液管理】
6. 【心不全の輸液管理】
7. 【急性脳障害患者の輸液管理】
8. 【腎不全の輸液管理】
↑【評価】および【治療】の項を参照
9. 【肝硬変・肝不全の輸液管理】
10. 【外傷と熱傷の輸液管理】
その他の巻についてもこちらをご覧ください↓
——————————————————————–
【1.体液動態】
[輸液の行く先]
・体液は体重の60%であり、そのうち40%が細胞内、20%が細胞外に存在する。
・20%の細胞外液のうち、血漿が5%、細胞間質液が15%である。
→細胞間質にはコラーゲンなどの高分子がゲル構造を取りながら存在しており、炎症の舞台となる。
→炎症によりゲル構造が変化することにより、細胞間質の水分量や水の移動速度が変化する。
・例えば晶質液(乳酸リンゲルなど)を血管内に投与すると、水は血管壁を介した静水圧と膠質浸透圧の勾配に従って、血管内から細胞間質へ速やかに移動する。
・細胞間質に貯留した水はリンパ管を通して血管内に戻る。
→晶質液の投与終了直後、血漿量は輸液の約40%だけ増加し、その後急激に減少する
→細胞間質に移動する分と尿排泄される分を考慮すると、投与終了2時間後には血管内にほとんどとどまらない。
[サードスペースとは]
・物理的に細胞内でも細胞外でもない“第三のスペース”が存在するわけではない。
・(私見)臨床現場では、細胞内でも血管内でもない、細胞間質のことを慣習的にサードスペースと呼んでいることが多いような印象を受けるが、実際には正確な表現ではない。
・実際には下記のようなことが起きている。
・炎症の存在下では、血管透過性の亢進により血管→細胞間質へ水分が移動する。
・加えて、細胞間質のゲル構造が変化し膨張することから陰圧を発生させ、hypovolemicにも関わらず、血管内から細胞間質へ能動的に水分が引き込まれてしまう。
・さらに炎症の存在下では、膨張したゲルの粘性により、水分は細胞間質を自由に動くことが出来ず、あたかも水分が固着されたような状態になる。
→これが「水分が血管内からサードスペースに逃げている」と言われる状態の本質である。
→逆に、炎症が鎮静化されると、細胞間質ゲルの粘性が低くなり、水分が自由に動けるようになる。結果的に、リンパ管を通して血管内へ水分が流入し、利尿期となる。
[輸液と低血圧]
(参考:https://www.jikeimasuika.jp/icu_st/161101.pdf)
・輸液は血圧を直接上げるのではなく、あくまでも、前負荷”を増やすことによって心拍出量を増やし、結果的に血圧が上がっているに過ぎない。(フランクスターリングの法則による)
・心収縮能が低下している場合は、前負荷が増えても拍出量が増えず、血圧が上がりづらい。

・敗血症性ショックの際には、血管が拡張し、輸液による前負荷の上昇が得られづらく、ノルアドレナリンによって血管収縮を行わなければ大量の補液が必要となってしまう。
・加えて、敗血症には高率に心収縮不全・拡張不全を合併することから、さらに前負荷の上昇が得られても、血圧の上昇が得づらいという特徴がある。
・対して、出血性ショックの場合には、生理的代償として血管が収縮しており、輸液に対する前負荷の上昇が速やかに得られるという特徴がある。
[従来の輸液動態モデルから現在の輸液動態モデルへ]
・従来の輸液モデルは、細胞内液・血管内・細胞間質という3つの間仕切りを設け、その間での輸液製剤の行き来がないものとして語られていた。

・細胞外液は細胞外(細胞間質と血管内)という仕切りの中で、決められた割合で分布。
・ブドウ糖液は、3つの部屋全てに、決められた割合で分布。
・膠質液は、血管内という1つの部屋のみに分布
→しかしながら、現在の研究によれば、実際に投与された輸液とその分布については、上記のコンパートメントモデルとは全く異なるものであることが分かってきた。
→従来のコンパートメントモデルよりも、実際に即したモデルとなっているのが、グリコカリックスモデルを基にした輸液動態である。
[グリコカリックスという概念]
・グリコカリックスとは細胞内皮の内腔表面に存在するプロテオグリカンの層である。
・グリコカリックスにより濾過される血漿がすなわち、血管内から細胞間質へと向かう血流(Jv)である。
・ただしアルブミンはグリコカリックスを透過しないことから、グリコカリックスの敷かれていない部分(large pore)から細胞間質へと向かう(Js)
・large poreを介して細胞間質へ浸透したアルブミンは、濃度勾配に従ってグリコカリックス直下に拡散する。
→これは、Jvとは逆向きのベクトルであることから、Jvはグリコカリックス直下の膠質濃度(πg)を薄める方向に働く。

①毛細血管圧(血管内volumeと血圧に依存)が低い場合
・Jvが低下することから、πgに対するJsの影響が強く、πgは血漿の膠質濃度(πc)と同等になる。
→この状態で晶質液を投与すると、膠質浸透圧較差がないことから、血管内に投与された晶質液の血管外移動が少なくJvが抑えられることから、血漿増量効果が強くなる。
→この状態で膠質液を投与すると、πc>πgとなり、浸透圧勾配が生まれ、一旦はJvが低下する(血管内volumeが上昇する向きに動く)が、結局Jsを通してπgが上昇してしまうことから、その作用は短時間に限られる。
②毛細血管圧が高い場合
・Jvが増加することから、グリコカリックス直下のアルブミンが希釈されπgが低下する。
→この状態で晶質液を投与すると、πcが希釈され、すでに大きく存在している膠質浸透圧較差(πc – πg)を小さくしてしまい、結果として血管外へ向かう水分が相対的に増え、相対的にJvが増加する。(圧較差が大きいほうが、Jvつまり水分の血管外漏出は小さく済むのに、圧較差を小さくすることによってJvが相対的に大きくなる)。つまり晶質液は血管内volumeを増やす向きには働かない。
→この状態で膠質液を投与すると、πcが上昇するが、そもそも毛細血管圧が高いことによるJvの増加からπgは希釈され低いままで保たれる。つまり膠質浸透圧較差は大きいまま保たれるため、結果的に大きな結晶増量効果を発揮する。

[敗血症による血管透過性亢進]
・サイトカインなどの炎症性物質がグリコカリックスを破壊し、水分やタンパク質が細胞間質に漏出しやすくなっている状態を指す。
→さらに大量輸液によってもグリコカリックスが傷害されることが分かっている。
・加えて、炎症による細胞間質ゲルの膨張により、水分が能動的に血管内から間質へ移動する。
・さらに、上図のlarge poreの数も増えることからタンパク質の細胞間質への移動も亢進する。
→πcは低下するが、Jvが増加していることからπgも低下し結果的にほぼ等しくなる。
→最終的には毛細血管圧の低下(毛細血管volumeの低下)によるJvの低下と、血管透過性亢進によるJvの増加が釣り合いJvは正常時とあまり変わらない。
・敗血症の初期は、hypovolemicと血管透過性亢進が同時に存在している。
→つまり、血管は拡張しているが、hypovelemiaであることから、毛細血管圧が低下する
→この状態では晶質液による血漿量増加効果が期待できる。
→しかしながら、その後、毛細血管にvolumeがいきわたり、毛細血管圧が上昇した後も晶質液の輸液を続けてしまうと、その水分は大量に細胞間質へと漏出してしまう。
→さらにノルアドレナリンによる過度な血管収縮は毛細血管圧を上昇させ、水分の細胞間質への移動を亢進させてしまう。
——————————————————————–
【2.輸液製剤の各論】
[①細胞外液]
・生理食塩水
→NaとClの濃度が血漿よりも高くなっている。
→大量投与で高Cl代謝性アシドーシスのリスクがある。
・リンゲル液
→NaとClの濃度が血漿の濃度により近くなっている。
→乳酸リンゲルで死亡・透析・腎障害の複合アウトカムが優れていた
→生食は高Cl血症によるアシドーシスやAKIのリスクがあり、大量投与は行わない
[②膠質液]
・アルブミンと人工膠質液であるHESが挙げられる。
<アルブミンを使用するかどうか>
(参考:https://drmagician.exblog.jp/21822362/)
晶質液に加えてのアルブミンの併用は平均血圧を上昇させ,心拍数を改善させ,循環作動薬・強心薬の使用期間を短縮し,初期7日間の体液バランスが有意に低いが,メインアウトカムである28日および90日死亡率に有意差はなかった。
(私見)→大量の晶質液が必要となりそうな場合に、intakeを減らす目的や、低Alb血症を併発している場合には積極的な使用を考慮しても良いかもしれない
< HESは使わない>
・HESは現場で良く使われているのは、ボルベンやヘスパンダーなど
・敗血症患者において、HESを使用した患者で死亡率の上昇や腎代替療法に移行した割合が多かった。(CHEST study)
→HES投与は予後を悪化させるものとして、現在では使わないことが推奨されている。
[③血液製剤]
・コンパートメントモデルによれば、投与した血液製剤はすべて血管内にとどまるとされていた。
・しかしながら、現在はグリコカリックスモデルを用いた輸液動態を考える必要がある
→その実際に動態については、詳しく述べている文献が現在のところ存在しない。
・輸血関連循環過負荷(TACO)や、輸血関連急性肺障害(TRALI)に注意する必要がある。
→CKD患者や心不全患者、輸血前の出血性ショックなどが強い発症リスクとなる。
→輸血の速度が速いほどリスクとなる。
・FFPは1単位120mL
→2単位240mLが1バッグとなっていることが多い。
・PCは1単位20mL
→10単位200mLが1バッグとなっていることが多い。
・RBCは1単位140mL
→2単位280mLが1バッグとなっていることが多い。
・外傷による出血性ショック時の輸血は
FFP:PC:RBC = 1:1:1 (単位)
・非外傷時は
PC:RBC = 1:2(単位)
——————————————————————–
【3.輸液必要性と反応性】
参考:https://drmagician.exblog.jp/24106425/
参考:https://www.jikeimasuika.jp/icu_st/161101.pdf

・上記のように前負荷の増加に応じて一回心拍出量が増加するが、前負荷がある一定レベルを超えるとむしろ一回拍出量は減少することも知られている。
・よって、一回心拍出量の増大が得られる前負荷の上限が輸液量の目安となってくる。

①CVP
・循環血漿量の予測指標としては不十分。
・その精密度は輸液の施行有無をコイントスで決めているのとほぼ同じ。
(Crit Care Med 2013; 41: 1774-81)
②ScvO2
・末梢組織の酸素利用障害によって、中心静脈の値であるScvO2が上昇する。
・ScvO2>70%が末梢循環不全の目安と考える。
③IVC径
・IVC径の変動によるfluid responsivenessの予測は様々な要因で偽陽性・偽陰性が生じる
・IVC径でカットオフ値を決めて定性的に評価するよりは、呼吸性変動の値(率)を定量的に評価するほうがまし。
→自発呼吸のあるショック患者で、呼吸性変動が42%以上あれば輸液反応性があると考える(ただし、そんなこと迷ってる暇がないことが多い)
④SVV
・動脈圧波形の呼吸性変動から算出される一回拍出量の変化
(循環血漿量が減少している状況では変動が大きくなる現象を利用)
・SVV>13で輸液反応性を期待する
・ただしSVVによるモニタリングは以下の状態を前提として用いる必要がある
〇不整脈がないこと
〇自発呼吸のないこと(人工呼吸器強制換気中であること)
〇一回換気量8mL/kg以上であること
・またSVVやPPVなどは、肺高血圧に伴って右室後負荷が強まっている際にも上昇することが知られている
→ARDSの20-25%に合併すると言われている、急性肺性心の状況で肺高血圧により右室負荷が強まっている状況においては、SVV, PPV > 13 の状況であっても、これが輸液反応性を示すのではなく、単に右室後負荷が強い状態を表していることがある
→SVV、PPVと合わせてPLR(後述)を行い、PLRによりSVV,PVVが低下するのであれば輸液反応性があると判断する。
⑤乳酸値
SSCGでも初期治療の指標となっており、乳酸クリアランス(初期値からの低下割合)が治療効果の指標とはなりうるが、組織の低酸素、低灌流を必ずしも反映しているわけではなく、循環の指標として使うことは難しそう。
→治療目標として乳酸クリアランス10%~20%(2hrごと)を目指すと生命予後が改善するかもしれない。
⑥PLR test(Passive Leg Raise test)

・測定手技
ⅰ. 45度上肢挙上からスタート
ⅱ. 患者に触ることなく、下肢を45度挙上する。
ⅲ. この状態で一分間待った後に心拍出量を計測(MAPの測定のみでは感度が低い)
ⅳ. 元の状態に戻して、心拍出量がもとの値に戻ることを確認(容量負荷という要因のみで拍出量上昇が得られていたことを確認)
・拍出量の評価方法
・TTE、動脈圧波形分析で拍出量を測定
→15%の増加を輸液反応性ありのカットオフ値とする
・etCO2で測定
→5%の増加を輸液反応性ありのカットオフ値とする
・動脈血圧で測定
→感度が低く、「輸液反応性がないこと」の証明には使えない。
・備考
ⅰ. PLRによる心拍出量の変化は、容量負荷による心拍出量の反応性を非常に正確に予測するが(特異度91%, 感度85%)、動脈血圧の変化の効果を評価すると、PLRテストの特異度は許容できるが感度は乏しかった(特異度83%, 感度56%)
→血圧は血管抵抗という因子によっても規定されているためカテコラミン使用下では不正確な指標となってしまう。
→また検査時の疼痛・咳嗽・不快などもカテコラミン誘発因子となり得る。
ⅱ. PLRの効果は1分を超えると減弱することから、それ以内に心拍出量の評価をする必要がある。
ⅲ. 頭蓋内圧亢進の可能性や、腹腔内圧上昇、腹部・下肢に疼痛がある状況では施行困難。
ⅲ. 一回心拍出量の増大が得られる前負荷の上限が輸液量の目安となってくる。
⑦Fluid Challenge
頭蓋内圧亢進患者や、疼痛、あるいは様々な理由でPLRが施行出来ない患者においては、実際に少量輸液負荷を実施して心拍出量の変化を確認。
・一回拍出量の測定
→左室流出路径(長軸像のAorta径)の2乗と平均流速に比例する。

⑧CRT:Capillary Refilling Time
ANDROMEDA shock trialより(http://hospitalist-gim.blogspot.com/)
・CRT:右示指末端の腹側で、スライドグラスを用いて10秒間、皮膚が白くなる状態で圧迫し、元の皮膚色に戻るまでの時間を計測。
・3秒以上を異常と定義する.
・CRTを測定することは、上記のような乳酸値のフォローによるものと同じ精確さで治療をモニタリングできる。
・ただしtrialでは30分毎にCRTを計測していた。
・またresponderに対しては、CRTが正常化するまで、その都度500mLの補液負荷をかけていた。
⑨TPTD
Trans Pulmobary ThermoDilution
(参考:https://drmagician.exblog.jp/24142691/)
・中心静脈カテーテルから冷水を注入し、動脈カテーテルによって動脈血の温度変化を測定することによって心拍出量を計算する。
・右心カテーテルによる熱希釈法と同様の原理を用いている。
・TPTD study(敗血症のTPTD管理 vs CVP管理)の中間報告では、人工呼吸器管理日数はTPTD群で有意に短縮された。
・カテコラミン投与期間についても,TPTD群ではCVP群と比較して日数が短縮される傾向にあった。
(追記:ただし、そもそもCVPの指標としての有用性が確実でないと分かったいま、「CVPよりも優れている」という結果にどれほど意味があるかは疑問である。)
・デバイスを新たに導入する必要があるが、それにより主に下記の指標を測定できる。
a. GEDV
・心臓拡張末期容量指数
→心拍出量は左室拡張末期容量に依存するというフランクスターリングの法則に基づいて有用性が生まれる。
・正常値は680~800mL/m2
→輸液負荷の前後でモニタリングすることでrespond/non-respondを評価できる。
b. EVLWI
肺血管外水分量指数
→肺水腫の程度を評価することが出来る。
・正常値は3.0~7.0ml/kg
——————————————————————–
【4.Septic shockに対する輸液療法のまとめ】
上記の指標のうち、現在エビデンスがしっかりしているのは、
①PLRによるresponder/non-responderの評価
②SVVによるresponder/non-responderの評価
(ただし、不整脈なし・機械換気中などの条件あり)
③乳酸値、CRTによる治療反応性の評価
であることが分かった。
これを踏まえて、総論的に輸液療法をまとめると、

——————————————————————–
【5.急性呼吸不全の輸液管理】
・ARDS患者に対しては、輸液量を制限し利尿を促進させるconservative strategyを行うことで、酸素化が改善し、人工呼吸期間が短くなる。
→いかに他臓器を障害することなく肺を軽くするかという観点がARDSの治療戦略にとって大事である。
[ARDSの病態]
・感染や外傷などの炎症によって生じる肺血管の透過性亢進によって、肺血管外水分量が増加して起きる非心原性肺水腫と考えられている。
・さらには、炎症性サイトカインなどの影響により、グリコカリックス(詳細は前述)の障害によって膠質成分の血管外漏出が亢進してしまう(通常large poreしか通過しない膠質成分が比較的自由に細胞間質へ漏出してしまう)ため、血管内膠質浸透圧が低下し、浮腫が増強されてしまう。
(心原性肺水腫は単純に毛細血管圧が上昇しJvが増加することによる水分漏出なので、違う病態)
→心原性・非心原性に関わらず肺水腫の病態においては、毛細血管圧を低く抑えることにより、水分の血管外漏出を極力少なくするconservative strategyが重要な治療戦略となる。
[conservative strategy]
・ARDSの血行動態安定期に、輸液を制限しつつ積極的な利尿を行ったconservative群は、輸液を制限せず利尿開始の閾値を厳しくしたliberal群と比べ(60日死亡率は改善しなかったものの)、人工呼吸器装着期間が短くなり、肺障害スコアの改善を認めた。
・中枢神経障害の有害事象もconservative群で有意に減少した
・その他の、肝腎障害については、(大まかにいえば)血行動態が安定し臓器血流が保たれている状態で利尿を行えば、有意な障害が起きない可能性が示唆される。
→逆に、十分な臓器血流が保たれておらず、臓器忍容性が低い状態で利尿をかけると臓器障害が進行してしまう可能性がある。
[フェーズごとの治療戦略]
・ARDSの原因は肺炎が59.4%、肺以外の感染症が16%である。
→敗血症の治療フェーズを重ね合わせることで理解がしやすい。
・①血行動態不安定期 ②血行動態安定期 ③人工呼吸離脱期に分けて考えるのが簡便であり、それぞれおおまかには
①不安定期:輸液反応性を評価したうえでの適切な輸液量管理
②安定期:臓器障害を起こさない範囲での積極的な利尿
③離脱期:SAT/SBTの開始基準と成功基準
を心掛けることが肝要である。
[①血行動態不安定期]
(参考:https://drmagician.exblog.jp/25135229/)
・近年EGDT(Early Goal Directed Therapy)に基づいたいわゆる「大量輸液療法」についてはその有効性を疑問視する論旨が多く見られる。
・循環動態の評価を無視した、惰性で行われる「大量輸液」は脳浮腫や腹部コンパートメント症候群をはじめとして、全身の浮腫につながり明らかに有害である。
・しかしながら、それは敗血症性ショックの初期蘇生で輸液負荷を行ってはならないという意味には全くならない
・以前に輸液量と死亡の関連性を自施設で後ろ向きに検討したことがあるが,敗血症性ショック疑いで初期大量輸液を行わなかった症例は死亡率100%であった。
(上記サイトより引用)
→・敗血症性ショックによる循環不全に対して、まずは30ml/kgのボーラス投与による初期輸液蘇生を行う。
→重要なのは、初期輸液負荷後に無駄な輸液を行わず、心拍出量を上げるメリットがあるとき(循環不全の所見があるとき)のみ、PLRにより輸液反応性の有無を評価して輸液を行うという戦略である。
(PLRについては上述参照)
→加えて、やや逆説的ではあるが、いたずらに輸液を制限してカテコラミンのみ
増量するような管理をしてもダメである。「迷ったら輸液をする」という金言を抱いておくことも重要である。
<急性肺性心という概念>
・ARDSの20-25%に合併すると言われている
・微小血栓や、低酸素血症による血管リモデリングや血管攣縮、アシドーシスや炎症性メディエーターなどを背景とした肺高血圧を指す。
・SVVやPPVなどの動的指標は、肺高血圧に伴って右室後負荷が強まっている際にも上昇してしまうことが知られている。
→急性肺性心の状況で肺高血圧により右室負荷が強まっている状況においては、SVV, PPV > 13 の状況であっても、これが輸液反応性を直接示すのではなく、単に右室後負荷が強い状態を表していることがある。
→SVV、PPVと合わせてPLRを行い、PLRによりSVV,PVVが低下するのであれば輸液反応性があると判断する。
<アルブミンを使用するかどうか>
(参考:https://drmagician.exblog.jp/21822362/)
SAFE study
ALBIOS study
・晶質液に加えてのアルブミンの併用は平均血圧を上昇させ,心拍数を改善させ,循環作動薬・強心薬の使用期間を短縮し,初期7日間の体液バランスが有意に低いが,メインアウトカムである28日および90日死亡率に有意差はなかった。
(私見)→大量の晶質液が必要となりそうな場合に、intakeを減らす目的や、低Alb血症を併発している場合には積極的な使用を考慮しても良いかもしれない
[②血行動態安定期]
・いかに絶妙に利尿をかけるか、いかに臓器の忍容性を評価して臓器障害を減らすかということに重きをおく。
・ただし、、、臓器忍容性を客観的に評価できるとstudyで示されているのは今のところ心エコーのE/E’だけである。
→(私見)実際には、CVP>8mmHgを1つの指標としてみたり、IVC径の呼吸性変動をみたり、PRL/SVVで輸液の必要がないことを確認したり(ただし心機能低下例でないことが前提)、ラボデータの肝腎機能を見たり、乳酸値で循環不全の具合を予測したり、身体所見で溢水/脱水を推測したりしながら、総合的臨床的に判断するのが妥当なラインなのかもしれない。
<ARDSの安定期とアルブミン+フロセミド>
・血行動態安定期にあり、積極的に利尿をかけたいにも関わらず、低タンパク血症を伴うことから除水が進まない患者に対しては、フロセミドの持続静注に加えてアルブミンを投与することによって、除水が有意に進み、かつ酸素化改善効果が有意に高くなる可能性がある。
→この研究の介入は、「フロセミド持続投与4mg/hrに加えて、25%アルブミン製剤25gを8時間おきに投与というもの」
(Martin et al. Crit Care Med 2005; 33:1681-7)
→上記のような血行動態不安定期に晶質液の代わりに投与するアルブミンとは扱いが違うので注意

https://www.jaccn.jp/guide/pdf/proto2.pdf
・SBTに失敗した際には、原因として体液バランスの増加や心機能低下による心原性肺水腫を考える。
→つまり除水がさらに必要かどうかを再評価する必要がある
・さらには、抜管が成功したとしても、陽圧換気からの離脱により左心負荷が増強することから、抜管前のvolume管理は厳密に行う(時に意図的にdry sideにもっていく)必要がある。
・低心機能でSBTの開始基準を満たした患者においては、BNPの値をガイドに抜管の成功/失敗を予測できるとしたstudyがある(Mekontso et al. Intensive Care Med 2006; 32: 1529-36)
→単施設RCTであり、参考程度に抜管前に測定するのが良いのかもしれない。
→同研究ではBNP200pg/mLをカットオフとして、超えた場合にフロセミドを投与し、BNPを下げるという介入を行った。
→(私見)頻回にBNPを図らなければならないというハードルが日本の実臨床では超えづらいかもしれない。
——————————————————————–
【6.心不全の輸液管理】
[Frank-Starlingの心機能曲線]
・循環器と輸液バランスについて学ぶ際に、最も基本的な概念となるのが、フランクスターリンの法則である。
・この法則は、「一回拍出量が左室拡張末期圧に依存する」ということのみならず、心機能低下例でグラフがY軸で負の方向へシフトし、左室拡張末期圧の上昇に比して、「拍出量の上昇がそれほど見込めない」ことなども表す。
・また曲線をNohria/Stevenson分類と組み合わせることにより、病態の理解がしやすくなる。
(Nohria Stevenson分類について、詳しくは「急性心不全」の【心エコー】の項を参照)


・つまり高度の不全心においては、利尿薬や血管拡張によって前負荷を軽減させ、曲線上の点を左方にシフトさせてしまうことのよって、dry-coldの低灌流状態に陥ってしまう可能性があることを示している。
[P-V loopとは]
・心臓が収縮してから拡張し、また収縮するまでの1回のサイクルを、各場面で描いたもの。
・縦軸が左室圧、横軸が左室容積となっている。

①P-V loopの幅
LVEDV – LVESV=SV
一回拍出量を示す。
②ESPVRおよびEes
・前負荷を変化させP-V loopを描くと、左上の収縮期点は直線状にならぶ。
・この直線をESPVR(End Systolic Pressure-Volume relationship)といい、その傾きをEes(End systolic elastance)という。
・前負荷や後負荷の影響力を受けにくく、基本的には心臓ごとに固有の曲線を有すると考えらえる。
→ただし、カテコラミンでEesは大きくなり、心機能低下時には小さくなる。
③EDPVR
End Diastolic Pressure Volume Relationship
拡張末期圧と拡張末期容積を表している。
→前負荷の程度を表している。
→LVEDVの増加によりLVEDPが緩徐に上昇するのが分かる。
以上の①②③及び、LVESVの4変数により、P-V loopが形成される。
[P-V loopの応用]
・患者のEDPVR(左室拡張期圧・容積曲線) がどのような形となっているか、利尿薬や血管拡張薬の反応をみながら、以下の3タイプに分類することで理解しやすくなる。
①急峻なタイプ
→HFpEFなどの拡張不全により、コンプライアンスが低下している例
②なだらかなタイプ
→HFrEFなどの収縮不全により、LVEDVが拡大している例
③全体が上にシフトしているタイプ
→心アミロイドーシスのように全体が上にシフトした例

①急峻なタイプ
・HFpEF(心収縮力が保たれた心不全)を始めとした、心室が固くなり拡張不全を呈している状態を表す。
(詳しくは「急性心不全」の【病態生理】参照)
・左室肥大や心筋線維化などが原因で心室コンプライアンスが低下しているため、同じLVEDVでもLVEDPが上昇してしまいやすくなる。
・前負荷の変化に対して、LVEDPが上昇しやすく、容易に肺うっ血を呈する。
②なだらかなタイプ
・HFpEF(心収縮が低下した心不全)に多い。
・慢性的に心収縮力が低下している場合、SVの低下を代償するために左室容積が大きくなる。また心筋リモデリングによっても左室が拡大している。
・「心室がたるんでいる状態」になっているので、LVEDVの上昇に比してLVEDPはあまり上昇しない。
・ただし、一定の用量を超えるとEDPVRの傾きは急峻になるため(後述するストレイン依存性)、水分貯留による慢性の前負荷増加でも左室拡大で代償できなくなるとLVEDPが上昇し肺うっ血を呈する。
③全体が上にシフトしているタイプ
・アミロイドーシス、一部の肥大型心筋症、虚血などではこのタイプとなる。
・心室コンプライアンスの低下や内腔狭小化などが関与し、同じLVEDVでも高いLVEDPとなることを示している。
・全体にLVEDPは高値を示すことから、肺うっ血を呈しやすい。
[PV loopで見る心不全の各病態]
a. 肺うっ血
・前負荷の上昇により肺うっ血をきたす。
・前負荷の上昇にはfast pathway とslow pathwayの二つの機序がある
①fast pathway 水分再分配型
・血管収縮による、前負荷・後負荷の増大が本態となる。
・クリニカルシナリオでいうところのCS1に相当。
<病態生理>
・後負荷増大に対する代償破綻などによってSVが低下すると、RAS系の亢進により動脈収縮が起き、さらに後負荷が増大する。
・同時に静脈収縮により、静脈灌流量が増大し、前負荷も増大する。
→静脈にpoolingされていた血液が血管収縮により体循環に移動することをcentral shiftと呼び、この前負荷増加の機序をfast pathwayという。
→からだ全体の水分量は変わらないが、末梢血管内の水分が心臓へ移動することにより前負荷が増加する。
・後負荷の増大及び、LVEDPの上昇により、P-V loopは下記のように右上へシフトする
→グラフから明らかなように、SVが低下する。

・またさらに、左室の前負荷が増大すると、僧帽弁輪の拡大によりMRが増加する
・またさらに、左室の後負荷が増大すると、大動脈圧上昇により、逆流量(つまりMR)が増量する
→その結果、SVは低下し、さらに左房圧の上昇によって肺うっ血が起きる。
< fast pathwayの水分管理>
・central shiftしてしまった血液を再び末梢に再分配することにより、前負荷を軽減させることが重要である。
→硝酸薬による静脈拡張で血液の抹消poolingを得る。
→硝酸薬は同時に動脈も拡張するため、後負荷の軽減ともなる。
→Ca遮断薬は、動脈の拡張により後負荷を軽減しうるが、同時に心収縮力の低下や反射性頻脈を呈することから、第一選択とはならない。
・central shiftによる肺水腫を利尿薬のみで治療すると、ますます末梢循環が悪化し予後不良となる。
・(追記)NPPVは左室の前負荷・後負荷どちらも軽減することから、fast pathwayの心不全治療に有効である
→NPPVによる陽圧換気により、胸腔内圧が上昇する
→左室を壁外から押す力が加わるので、収縮力が上昇し後負荷に対抗できる。
→陽圧換気により、肺血管抵抗が上昇し、左房灌流量が減少することで、左室の前負荷が減少。
→陽圧換気で右室圧が上昇することで左室拡張末期容積が減少する。
②slow pathway水分貯留型
・クリニカルシナリオでいうところのCS2に相当
<病態生理>
・水分貯留による前負荷増加が本態となる
・心拍出の低下による腎血流の低下や腎輸入細動脈の収縮などにより、水分・塩分貯留が起きる。
→静脈灌流量の増加が起きる
→RAS系は慢性的な亢進状態となっており、圧受容体の感受性低下やダウンレギュレーションが起きる
<slow pathwayの水分管理>
・利尿薬による前負荷軽減
・ループやトルバプタンを使用する
・実際にはfast/slow pathwayが混在しているので、血管拡張+利尿という治療をすることも多い。
b. afterload mismatch
・後負荷とは、末梢血管抵抗と大動脈コンプライアンスなどにより規定される。
→最も大きな規定因子は末梢血管抵抗である。
・血圧が上昇し後負荷が増大すると、正常心では代償機能が働く
→すなわち、カテコラミン分泌によってEFを維持させたり、前負荷を上げて収縮力を維持させたりする。
→代償機構を使い果たすとEFや心拍出量が低下し、このような状態をafterload mismatchという。後負荷に対応するだけの十分な収縮を行えずSVが低下する。
c. 拡張障害
①EDPVRに依存して、EDPVR上を左にシフトするタイプの拡張不全
②EDPVRに依存せず、EDPVRの上方に移動してしまうタイプの拡張不全
の2種類がある。
・実臨床では二つ病態が入り混じって存在しているが、どちらの病態が主体となっているかを踏まえて治療介入することが重要である。
・不用意で惰性的な利尿薬投与は、時に心拍出量を低下させ、容易にLOS(Low Output Syndrome)の病態を招く。


①ストレイン依存性(EDPVR依存性)
・原則的には、前負荷の上昇により、グラフが右にシフトした場合、SV(一回拍出量)は増加し、特に問題は起きない。

・しかしながら、ある一定程度の容積負荷を超えると、EDPVRの傾きは急峻となり、心室コンプライアンスが低下することにより、わずかな容積の上昇で急激に左室圧の上昇をきたすようになる。

→これによって起きるのがストレイン依存性の拡張障害である。
→特徴として、心室筋自体の性質は変わっていないことが挙げられる。
→治療としては、利尿薬や血管拡張薬、NPPVにより曲線上を左にシフトさせてあげればよい。
②ストレイン非依存性(EDPVR非依存性)
・心筋そのものの拡張特性が変化する場合や、左室外(心膜や右室)からの圧排により左室心筋自体が変化したわけではないのに拡張能が障害されるものなどがある
→EDPVR上を動くのではなく、EDPVR自体が上方へシフトしてしまう。
→左室容積は同様にも関わらず、左室圧は上昇してしまっている状態となる。
→肥大型心筋症や心アミロイドーシスは不可逆的に変化してしまっているが、虚血や肺塞栓、収縮性心膜炎では原病の治療により可逆的になり得る。
<虚血性心疾患による拡張不全>
・虚血性心疾患による循環不全は
①虚血による収縮力低下(Eesの低下)
②虚血によるコンプライアンス低下によりEDPVR全体が上方へシフトする
の2つが同時に起きることによって引き起こされる。つまり収縮/拡張不全が同時に起きている。
→さらに、交感神経やRAS亢進により動脈収縮が起き、後負荷は増大する。
→静脈の収縮により、血液のcetral shiftが起き、前負荷が増大する。
→治療としては、硝酸薬の使用やNPPVの使用が有効であるが、薬物的治療で改善が乏しければすぐさま血行再建を行わなければならない。

<肥大型心筋症によるうっ血>
・肥大型心筋症では、EDPVRが上方へシフトしており、通常と同じ容積でも左室圧が上昇した状態にある
・この状態で前負荷や高負荷が増大し、ストレイン依存性の拡張障害も加わると、グラフの右上へシフトすることにより、LVEDPは容易に増大し、肺うっ血をきたす
・これらの疾患では、左室腔が小さく、EFにかかわらずSVが小さいため、容易にLOSの状態となる。
→利尿薬の投与により、グラフの左方へシフトさせようとしても、うっ血があまり改善しないのに容積が低下してさらにCOが低下する。
→グラフの右へ行くもだめ、左へ行くもだめ、という非常に治療に難渋する状態となる
→根本治療は心臓移植のみ。

d. 弁膜症
< AR>
・ARでは拡張期に大動脈から左室への逆流による容量負荷が問題となる。
・ただし、急性ARと慢性ARでは血行動態への影響が全く異なる。
①急性AR
・急性ARは大動脈解離や感染し心内膜炎などの外的要因により急激に発症する。
・急性の肺うっ血や低拍出による低血圧やショックをきたし重症となる。
→主な病態は急性の逆流による容量負荷と(逆流が多いことによって結果的に)SVの減少である。
→逆流によりLVEDPが高くなることにより、左房の収縮圧よりも高くなってしまうと、僧帽弁閉鎖のタイミングが早まり、左室の完全な充満が得られなくなる。さらにSVが低下する。
→水分のcentral shiftにより前負荷が増大しているが、解除しようと利尿薬を使うとますます末梢循環が悪化する。
→外科的介入が必要となるケースが多い
→IABPはdiastolic augmentationにより拡張期に大動脈→左心室側へ血流を押し込みARを悪化させるため、使用しない。
②慢性AR
・慢性ARでは逆流に対して代償性に左室が肥大しSVは維持されている。
→末梢循環は維持できていることから、非代償期になりうっ血をきたしても、利尿薬の投与でLOSになることは起きにくい
<MR>
・AR同様、MRにおいても急性/慢性によって病態が異なる。
・MRでは、収縮期に左房への逆流があることから、EF自体は上昇する。
→本来の後負荷である大動脈圧と比べて、左房に血液を逃がす時の後負荷が低いので、血液を左房へ逃がすと、左室が楽になる
→EFが高く見える。
①急性MR
・心筋梗塞後の合併症など、乳頭筋/腱索の断裂が原因で急性のMRが生じる。
・左房も左室も、もともとの拡大がないため、急激な左室→左房への逆流によりSVの低下および左房圧の上昇による肺うっ血(電撃性肺水腫)をきたす。
→交感神経、RASの亢進により急激なcentral shiftが起きる。
→急性ARの際と同様、急激な肺水腫に対して利尿薬のみで治療をしようとすると、容易にLOSに至る。
→多くの場合、外科的治療が必要。
→内科的治療はIABPにより、左室後負荷を軽減させることによりMRを減らし心拍出量を増加させる。
②慢性MR
・慢性の経過により、逆流に対して左房が代償性に拡大する
・左房が拡大していることにより、逆流による左房への容量負荷がかかっても左房圧は上がらず、肺うっ血にならない。
・血液が大動脈側へ駆出されず、左房に逃げることにより、左室に対しても容量負荷がかかる
→代償期には左室が楽に動いて話は終わるが、非代償期には左室腔の拡大が起き(Ds>40mm)、収縮力が低下する
→前述のように、MRの存在下でEFは70%など上昇しているので、たとえEF55%程度の心機能でも、収縮が低下していることを意味し、手術適応となる。
・内科的治療としては利尿薬・血管拡張薬を考慮する。
<まとめ>
このように、急性/慢性AR・MRで病態は全く異なり、急性弁膜症に対しては容易にLOSをきたすことから利尿薬の投与は行いづらい。
——————————————————————–
【7.急性脳障害患者の輸液管理】
・急性脳障害とは、脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)に外傷性脳損傷、蘇生後脳症や痙攣重責などを加えた概念
・生き残った脳細胞のために適切な血流を維持するとともに、脳浮腫を増悪させないことにも留意しなければならない。
[病態生理の総論]
①脳血流量と脳灌流圧
・脳血流は脳灌流圧(CPP: Cerebral Perfusion Pressure)によって駆動されている。
・CPPは平均動脈圧から頭蓋内圧を引いた値により求められる。
・CPPが一定であれば、脳血流量(CBF: Cerebral Blood Flow)も一定に保たれるが、CPPが変化した際には、自動調節能により血管径が変化することによってCBFを一定に保つ機構が存在する。
→急性脳障害が起きると、この自動調節能の働きがピーキーになり、致命的なCBFの減少/増加が正常脳よりも起きやすい状況となる。
②頭蓋内圧
・CPPの直接モニタリングが不可能なため、
CPP=平均動脈圧(MAP) – 頭蓋内圧(ICP)
という式を利用する。
・頭蓋内圧の構成成分には、脳実質・脳脊髄液・血液などが挙げられ、どれか一つの容積増加に対して、他の成分が代償的に容積減少をきたすことによって頭蓋内圧を一定に保つ機構が存在する。
・ただし、頭蓋骨は固く柔軟性がないことから、脳浮腫などにより内容積がある臨界点を超えて非代償性になると急激にICPが上昇してしまう。
→逆にいうと、頭蓋内圧亢進症に対して、容積をわずかでも低下させれば、急激にICPを下げることができる。
③体液シフトと脳浮腫
a. 浸透圧と体液シフトを理解する
・上述のように、体液の所在というのは
①細胞内
②細胞間質
③血管内
の3つに分けて考えることができ、そのうち①を細胞内液、②③を細胞外液と呼称する。
<通常の体液動態>
・浸透圧を規定する物質はNaなどのイオン、Glu、BUNなどが挙げられる。
・各スペース間の浸透圧は、各スペースにおける物質の浸透圧(「絶対浸透圧」)を合計した値となる。
・各スペース間の水分の移動は、各スペースにおける物質の張度によって規定される
→張度とは「有効浸透圧」とも言い換えられ、つまり物質の移動が制限されることにより各スペース間に濃度勾配が生まれ、結果、水分の移動を二次的に生み出す仕組みのことである。
→BUNは全てのスペースを自由に移動するため、水分の移動を規定する濃度勾配を生まず、張度を持たない。
→細胞内/間質では、NaやGluの移動が制限されることから、そこに濃度勾配が生まれ、NaとGluの濃度=張度に依存して細胞内/間質の水移動が規定される。
→間質/血管内では、NaやGluは自由に移動できるため、濃度勾配を生まない。
(普段、輸液による血管内volume多寡の議論をする際には、Na濃度に従った細胞内/間質の水移動を議論していることに留意。間質/血管内の移動ではない。間質/血管内はNaが自由に移動することから、濃度勾配を生まず、結果水の移動も生まない。)
→アルブミンは前述のグリコカリックスモデルに従って移動が制限されることから、そこに濃度勾配が生まれ、アルブミンの濃度=張度に依存して間質/血管内の水移動が規定される。

<BBBでの体液動態>
・通常の血管内皮細胞には間隙があり、そこを通してNaやGluが移動するが、脳血管においてはBBBが形成されており、tight junctionにより血管内皮の間隙がない状態が作られている
→通常の血管では間質/血管内をNaやGluが自由に行き来していたが、BBBでは制限がかかる。
→結果として、NaやGluの移動が制限されることから、そこに濃度勾配が生まれ、NaとGluの濃度=張度に依存して間質/血管内の水移動が規定される。
→つまり、頭蓋内圧亢進患者に治療として高張食塩水やマンニトールなどの高張液の投与をすると、血管内濃度が高まり、間質を介して最終的には細胞内から血管内への水の移動を促し、脳実質の容積を減少させることが考えらえる。

b. 脳浮腫の病態
・脳浮腫の病態として
①細胞毒性浮腫
→虚血などにより、水とナトリウムが細胞外から細胞内へシフトしてしまう細胞内浮腫。
②血管原性浮腫
→BBB(Blood Brain Barrier)の破綻のより水とアルブミンが血管内から細胞間質へシフトしてしまう間質浮腫
の2種類が混在している状況が考えられる。
[病態ごとの輸液各論]
①外傷性脳損傷
a. 圧管理
・いくつかのRCTやretro studyにより、外傷性脳損傷患者に対してCPPを高めよりも低めでコントロールする方が予後が良いとされる。
・さらに、高張食塩水とマンニトールを比較すると、食塩水のほうが治療成功率が高い可能性がある
・これらを踏まえBTFガイドラインでは以下のようになっている。
→CPPは60-70mmHgで管理
→マンニトールなどの高張液はICPを低下させるかもしれないが、臨床的転帰の改善を示すエビデンスが十分でなくコメントなし
b. 輸液製剤
・等張晶質液が第一選択
・アルブミンは有害
→アルブミン製剤が比較的低張であり、細胞毒性浮腫を増悪させたり、破綻したBBBを介してアルブミンが漏出し、血管原性浮腫を増悪させたりする可能性が示唆される。
②脳梗塞
・治療対象は血栓塞栓に加えて脳浮腫。梗塞に陥っていない虚血脳細胞の救済
a. 血液希釈に関するエビデンス
・脳梗塞患者ではしばしば脱水による血液濃縮がみられ、濃縮による血栓傾向が梗塞範囲の増大や死亡率の上昇と関連していると考えられてきた。
→これに対して、輸液による血液希釈により微小循環を改善させようとする治療が行われてきた
→しかしメタアナリシスにより、生命予後や神経学的予後の改善に有用性なしの結果。
・脳梗塞患者においては、細胞毒性浮腫によりほぼ前例で脳浮腫が起こるため、低張液(細胞内液よりも浸透圧の低い輸液、1号液や3号液など)を避けるべきである
・では逆に、高張液の予防投与により、積極的に細胞内液を間質へ移動させる治療にエビデンスはあるのだろうか
→エビデンス乏しい。
・結局、脱水や低張液を避けるのは当然として、血液希釈や予防的高張液投与を支持するエビデンスに乏しいことを考えると、脳梗塞患者への輸液の基本は等張液(細胞外液)によるeuvolemia管理であると考えらえる。
b. 圧管理
・ルーチンでのICPモニターや予防的な浸透圧利尿は推奨されず、輸液管理には等張液の使用を考慮する。
c. 治療的高張液の投与
・「予防的」高張液ではなく、「治療的」高張液
・脳梗塞患者の脳浮腫に対して、高張液の使用が臨床的転帰に与える影響について調べた質の高い研究はほとんどない
→あくまでも開頭減圧術施行までの一時的治療との位置づけとなる。
d. 脳梗塞患者のアルブミン投与
・アルブミンに脳浮腫を軽減し、微小循環を改善させる効果が期待されALIAS studyが実施された。
→25%アルブミンの投与群で90日後の神経学的予後に有意差なし
→25%アルブミンの投与群で症候性頭蓋内出血、肺水腫・うっ血性心不全の発生率が有意に高かった。
→現状、脳梗塞患者に対して神経保護作用を期待しての高容量アルブミンは投与してはいけないと考える。
③くも膜下出血SAH
a. 予防的hypervolemiaにエビデンスなし
・SAHでは体液の恒常性を保つ機能が失われやすく、多くの患者がhypovolemiaに傾きやすい。
・さらにこの体液バランスの異常は、血管攣縮やDCI(遅発性脳虚血)の誘発因子となり予後不良と関連すると考えられる。
・最初の出血から3-14日後に起きる限局性の神経障害や認知障害を指す疾患。

→この病態を避けるため、予防的hypervolemiaの治療が現在まで行われてきた。
→現在では2つのRCTにより、予防的hypervolemiaは輸液量を増やすだけで、遅発性脳虚血の発症を予防しないことが示された。加えて心肺関連合併症が増加。
→予防的にはhypervolemiaにする必要はなく、euvolemiaで管理する。
b. 治療的hypervolemiaにもエビデンスなし
・治療的hypervolemiaと治療的hypertension
→DCIを発症した後の治療について、治療的hypervolemiaには脳循環改善効果は期待できず、むしろ有害である可能性が複数の研究により示唆されている。
→現在の推奨はeuvolemiaで血圧を高めに保つ治療的hypertensionとなっており、CBFの増加効果が示唆されている。

https://www.jikeimasuika.jp/icu_st/160524.pdf
c. 輸液製剤の検討
・SAHでは中枢性塩類喪失症候群(CSWS)により、低Na血症を伴ったhypovolemiaに傾きやすい。
→水分制限や低張液の投与を避ける。
→ステロイドの投与がナトリウムと循環血漿量の維持に有効であるとの報告もあり、その使用を考慮する。
・HES製剤はsepsisの際と同様、SAHにおいても有害であり、使用しない
・アルブミンの投与はその効果の検証が不十分
→まずは等張晶質液の投与を
→生理食塩水は高Cl性アシドーシスのリスクがあることから、大量補液に使わない。リンゲルでも低Naの発生は増えない。
④頭蓋内出血
・脳出血に対する輸液及び圧管理に関する研究は少ない。
・ICPモニタリングの施行により頭蓋内圧亢進を呈した脳出血患者で神経学的予後との関連が見られなかった。
→ICPモニタリングの意義自体に疑問が残る。
・管理の実際としては外傷性脳損傷のガイドラインを参考にCCP=60-70mmHg程度で管理を行う。
・脳出血患者のICP上昇に対して、高張液による治療が行われるが、有効性に確固たるエビデンスがないのが実情である。
[急性脳障害における循環血液量の評価]
・急性脳障害ではhypervolemiaでもhypovolemiaでもなく、euvolemiaを目指すべきである。
→上述のように、hypervolemiaでもCBFの有意な上昇が得られず、心肺関連合併症が増えるだけ。
・【輸液必要性と反応性】を参考に行う。
——————————————————————–
【9.肝硬変・肝不全の輸液管理】
[肝硬変の病態]
・慢性肝疾患から肝硬変へ進行する過程で、細胞の繊維化、血管新生・血管閉塞による壊死が引き起こされる。
・NOなどの血管拡張物質が十分に放出されず、同時に交感神経系・RAS系の亢進により血管収縮が引き起こされる。
→肝血管抵抗の上昇により、門脈圧亢進が起きる。
→門脈圧亢進により、血流が内臓へシフトし血管拡張及びうっ血を呈する。
・低アルブミン血症により血管内volumeは間質へシフトし、有効循環血漿量が低下する。
→心臓は代償性にhyperになり、最終的には交感神経・RAS・ADHが亢進する。

[肝硬変の循環不全]
・心臓はhyperdynamicとなり心拍出量は増加しているが、末梢血管が拡張していることから血圧は低下傾向となる。
・血管内volumeが間質および腹腔などの体腔へ漏出しており、有効循環血漿量が減少している状態である。
a. 低ナトリウム血症
・RAS系の亢進による体液貯留傾向、さらにADHの分泌亢進により、希釈性の低Na血症を呈する。
→まずは血管内脱水が併存している場合には細胞外液投与により有効循環血漿量を保つ。
→腹水コントロール目的の利尿薬はすぐに中止する。
→有効循環血漿量が維持されている場合には、理論的には水制限が有効であるが、実際の重症患者では難しいことも多い。
・すでに痙攣や意識障害などの有症候性の低Na血症に対しては、通常通り高張性食塩水の投与により補充を行う。
→低Kがあれは合わせて補正することでNa濃度が上昇しやすくなり、アンモニア産生も抑制することができる。
b. 肝腎症候群
・内臓血管拡張と有効循環血漿量の減少により、結果として腎血管収縮・腎血流低下が起き腎機能障害に至る。
・非代償性肝硬変の診断から1年で18%, 5年で39%に合併する。
・根治的な治療は肝移植のみ
・血管内脱水はさらなる腎機能障害を引き起こすため避ける。
→アルブミンの投与も考慮されるが、明確なエビデンスはない。
・HESはここでも推奨されない。
c. 腹水
・肝硬変患者の循環不全に対して、細胞外液投与を行い、最終的に腹水が増加してしまうということはしばしば経験される。
・まずは循環不全に対して、通常の重症患者と同様に細胞外液にて蘇生を行い、腹水がコントロール不能となった際にはドレナージを行うというのが現実的なプラクティスとなる。
→細胞外液による蘇生は、併存しうる肝性脳症に対しても治療となりうる。
→この際にアルブミン投与が有効である可能性があり、使用が推奨される。
→分子鎖アミノ酸の輸液製剤については、研究上は効果がないとされているものの、臨床では頻用される。
d. アルブミンのエビデンス
・ICUに入室する重症患者において、アルブミン製剤による死亡率低下を示したRCTは今のところ存在しない。
(参考:https://drmagician.exblog.jp/21822362/)
・敗血症の例
晶質液に加えてのアルブミンの併用は平均血圧を上昇させ,心拍数を改善させ,循環作動薬・強心薬の使用期間を短縮し,初期7日間の体液バランスが有意に低いが,メインアウトカムである28日および90日死亡率に有意差はなかった。
(私見)→大量の晶質液が必要となりそうな場合に、intakeを減らす目的や、低Alb血症を併発している場合には積極的な使用を考慮しても良いかもしれない
・ただし特発性細菌性腹膜炎(SBP)の例では予後を改善しうるエビデンスがある。
→SBPによる循環不全により急速進行性の腎障害が合併する
→アルブミンと抗菌薬を投与することにより腎障害および死亡率が改善。
・急速に進行する肝腎症候群に対しては、昇圧薬に加えてアルブミンを併用することで腎障害改善に有意差があり、動脈圧上昇、RAS系抑制の所見を認める。
→第一病日に1g/kgの投与、その後20-40g/dayの投与を続ける。
・大量腹水穿刺(具体的には5L以上)の際に、アルブミンを投与することで、その後に起きうる低血圧、腎障害、低Na血症、肝性脳症など一連の症状が軽減されるという報告がある。
→腹水1Lごとに4gのアルブミンを投与
(ガイドラインでは8g/Lの記載があるが、非盲検RCTで4g/Lと効果に差がないことが言われている。)
e. 大量腹水穿刺
・腹水はACS(Abdominal Compartment Syndrome)のリスクとなり、ICUにおいても注意を払う必要がある。
・大量の腹水によってIVCが圧排され、血圧低下をきたす。
・横隔膜の圧排により換気障害も起きうる。
①診断的腹水穿刺
・腹水穿刺により腹水の質的診断を行う。
・SAAGや腹水培養、腹水Gram染色など


https://www.slideshare.net/katsushigetakagishi/ss-16188882
②治療的腹水穿刺
・難治性腹水の対しては、腹部膨満・胸郭圧迫による呼吸障害などの症状軽減目的に、治療的腹水穿刺を第一選択で行う。
→ただし、一度に大量の腹水を除去した場合に、低血圧、腎障害、低Na血症、肝性脳症なおど一連の症状を呈することがあり、最初は1L程度から始めて、徐々に排液量を増やしていく。
<腹水穿刺時のアルブミン投与>
・大量腹水穿刺(具体的には5L以上)の際に、アルブミンを投与することで、その後に起きうる低血圧、腎障害、低Na血症、肝性脳症など一連の症状が軽減されるという報告がある。
→腹水1Lごとに4gのアルブミンを投与
(ガイドラインでは8g/Lの記載があるが、非盲検RCTで4g/Lと効果に差がないことが言われている。)
[急性肝不全の病態]
・日本においては、急性肝不全の原因はB型肝炎が最多。
・アセトアミノフェンなどによる薬剤性肝障害も起きうる。
・肝硬変のような慢性の経過をたどっていないため、肝血管抵抗の増大や門脈圧亢進の症状はない。
(ただしB型肝炎が背景にある場合には、慢性変化を認める場合も当然ある。)
→急性の経過で、大量の肝細胞が壊死し、炎症性サイトカインおよびDAMPsが全身を駆け巡り、敗血症様の全身性炎症反応をきたす。
→最終的には脳浮腫をはじめとした多臓器不全をきたす。
→敗血症におけるSIMDと同様に、急性肝不全によっても心臓は代償性にhyperdynamicになり、潜在的には心筋症を合併している場合がある。

[急性肝不全と循環不全]
・通常と同様に細胞外液による蘇生を行う。
・目標値はMAP75mmHg以上、脳灌流圧CCP60-80mmHgなどが挙げられる。
・昇圧の第一選択はノルアドレナリン
・蘇生はCPPを意識した管理を行うことととなり、MAPの目標値が敗血症とは若干ことなるが、その大まかなプロトコルはおおむね敗血症に準じる。
a. バソプレシン
・CPPの上昇が得られないときには、ノルアドに追加してバソプレシンの投与を検討する。
・バソプレシンはCPPを上昇させつつも、頭蓋内圧亢進効果は乏しい可能性が示唆されている。
→(追記)急性肝不全の潜在的心筋症がSIMD(Sepsis Induced Myocardial Dysfunction)のようなものと同等であるとすれば、びまん性の心収縮力低下をきたしている心臓に対しては、バソプレシンの投与により病態が増悪する可能性がある。
→SIMDではこういった際の昇圧はノルアドレナリン+アドレナリンにより行う。
(参考:http://敗血症.com/assets/2017_symposium_03.pdf)
b. ヒドロコルチゾン
・急性肝不全の症状として、相対的副腎不全が挙げられるため、投与を検討する。
・ADRENAL studyと同様に、生存率の改善は示せてはいないが、ノルアドレナリンの必要量を減らす効果があるとされている。
——————————————————————–
【10.外傷と熱傷の輸液管理】
[外傷出血の病態生理と輸液療法]
・出血による循環血漿量減少性ショック及び、それによる臓器不全もさることながら、急性凝固障害の存在も重要である。
①大量輸液・赤血球輸血による凝固因子希釈
②低体温・アシドーシスによる凝固因子。血小板の活性低下
上記に加え、近年ではグリコカリックスの破綻が凝固障害に関連している可能性が示唆される。
・従来の、低体温とアシドーシス予防に重点を置いた蘇生法から、凝固異常予防にも重きを置いた蘇生法へ(死の三徴)
→重症外傷例における凝固異常は、受傷直後から存在しており、積極的な補正が死の三徴への進行を防ぐカギである
・晶質液の大量輸液の弊害を鑑み、sBP90mmHgを目標とするpermissive hypotensionと新鮮凍結血漿の高比率投与の有効性が考えられる。
・病院前輸液療法は、静脈路の確保に時間がかかるなどの問題があり、都心ですぐに病院搬送が可能な例においては、必ずしも推奨されない。
<外傷蘇生のゴール>
・バイタルサインや尿量の安定が得られても、組織への酸素の供給が十分であるとは言えない。
・ゴールドスタンダードはない
・(追記)急性期の蘇生が終わったら、乳酸値、BE を確認する。これらの正常化は蘇生が順調であり新たな出血はないことを示唆する。
(参考:http://www.nishiizu.gr.jp/intro/conference/h30/conference-30_02.pdf)
<輸液・輸液療法の選択>
・ICUにおける輸液蘇生時の、生理食塩水 vs 4%アルブミンは死亡率、臓器障害の頻度に有意差なし
・外傷患者に限ったサブグループ解析では、アルブミン投与群で死亡率が高い傾向にあった。ただし有意差はなし
→現時点で積極的な膠質液の投与は推奨されない
・(追記)
「外傷で出血するとアドレナリンにより毛細血管が収縮し組織が低酸素となり破壊されます。これに大量輸液すると、心筋梗塞時のtPA投与による再灌流みたいにischemia-reperfusion injuryが起こり、オキシダント、サイトカイン、炎症仲介物が大量に全身に環流し臓器障害、炎症、免疫抑制を起こすと言うのです。」
また大量輸液は腹部、四肢のコンパートメント症候群、炎症、ARDS、多臓器障害を起こします。また大量輸液で凝固因子が希釈され凝固障害も起こします。
晶質液(crystalloid:生食、乳酸リンゲル)の輸液過剰により酸素運搬能低下、 凝固因子濃度の低下が起こります。また輸液で低温になると熱、エネルギーが失われます。
酸性晶質液(生食の Ph4.5-8.0、乳酸リンゲル Ph6.0-7.5)の過剰で低還流による酸性度は更に悪化し、凝固因子阻害、悪循環(vicious cycle)の凝固障害、低体温、酸性となります。
なお蘇生にアルブミン、高張食塩水、高張デキストランの使用は生理食塩水に比べて 利点はありません。
(参考:www.nishiizu.gr.jp/intro/conference/h30/conference-30_02.pdf)
・外傷に大量輸液を行うと、生体外由来のミトコンドリア破壊産物(DAMPs)が全身に拡散され炎症、凝固障害を起こす。
・生体にとっては細菌感染も外傷も似たようなものということになります。
・出血性ショックから死亡までのmedian time(中央値)は2時間。
・患部に対しては、局所圧迫が有効でなければ止血帯が推奨される。
・駆血帯の上、輸液制限し即座に病院搬送、sBP80-90、最終処置まで輸液控えよ!
・ultrarapid “scoop and run concept” : 警察が駆血帯して病院搬送。
・出血性ショックから死亡までの中央値は2時間!
・最終的止血処置まで輸液を控えることは生存率を改善!
・病院前治療は意識と橈骨脈拍を保つ(sBP80)少量の生食・乳酸リンゲルの投与!
・最初の6時間内の晶質液輸液は3ℓ以内に留めよ!
・輸血は全血または赤血球:血小板:血漿は1:1:1。
[熱傷の病態]
・重症熱傷の主たる病態は、熱傷部位と非熱傷部位からのタンパク・血症の漏出にある。
・熱傷部位では微小血管障害により水とタンパク質が間質へ漏出する
→さらに間質のコラーゲンなどの気質組織が炎症により粘稠度を増し、間質に水分がトラップされる
・非熱傷部位においても、熱傷の影響で動員された炎症性メディエーターによりグリコカリックスが破綻することにより血管透過性が亢進し、タンパク質の漏出が加速される。
→これらの病態により、最終的には循環血液量減少性ショックを起こし、多臓器不全に至る。
→循環血漿量を確保しつつも肺うっ血やACSなどを回避するマネジメントが求められる。
→熱傷輸液管理においてもpermissive hypovolemiaの概念が有用となる。
[熱傷の輸液療法]
①初期輸液製剤
・晶質液により行う(乳酸リンゲル)
・必要輸液量が多くなり、大量輸液による弊害が懸念される場合には、アルブミンの投与を検討する。明確なエビデンスなし。
・高張食塩液やHESは有効とするエビデンスなし。有害である可能性あり。
・晶質液へのFFPの併用は、晶質液単剤と比較して輸液量を減らし、腹腔内圧を減少させる可能性があり、投与を検討しても良いかもしれない。
②輸液蘇生の開始基準
・成人では全体表面積の20%以上
・小児では10%以上
→ただし、当然個別に必要性を評価する
③輸液量の計算
・2-4mL/kg/熱傷面積(%)
→現在2mLと4mLを比較する多施設共同試験が行われている。
→2mLで輸液量が減っても生命予後に関連がない可能性もある。
→米国ガイドラインでは2mLを推奨(2008年)
④輸液療法の指標
・尿量を用いる。
→成人は0.3-0.5mL/kg/hr、小児は1mL/kg/hr
→CVPやPCWPと比較して、尿量モニタリングで死亡率に差なし。
・輸液速度は臓器灌流を保つ最低限の量とする。
→計算された量の1/2を最初の8時間、残りの1/2を16時間で投与するとするガイドラインがある。
川良健二
その他の巻についてもこちらをご覧ください↓