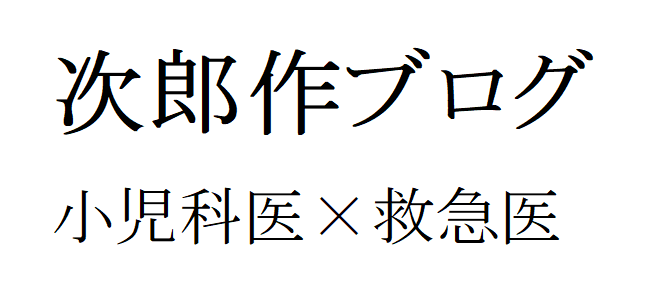医学部ではたくさんのことを学んだ。しかし、死は学んだうちに入っていなかった。
中略
加齢や老衰、死について、教科書はほとんど何も触れていない。
どのようにして死が訪れるのか、死にゆく人はどんなことを経験するのか、
そしてまわりの人たちはどのような影響を受けるのか、こうしたことは知るべき項目から外されていた。
自分たち学生にとっても、また教授たちにとっても、医学教育の目的は命を救う方法を教えることであって、命が尽きるのを手助けすることは関係ない。
”死すべき定め” 冒頭より引用
僕は、以前ある記事を書いた。
いや、正確には書こうとして、下書きのまま放置している記事があった。
担当していた患者が亡くなった時に感じた気持ちを、
「死」について考えたことを、
何とか言語化しようとしてもがき苦しんで、諦めていたことが実はあったのだ。
その時の、いわばお蔵入りとなった記事の内容も、
奇しくもこの著書の冒頭と似たものであった。
”僕は、人の命を救いたいと思って医師を志した。
医学部6年間「人の命を救うため、病気を治すため」に勉強してきたはずだった”
本屋で何気なくこの本を手に取って、先ほどの冒頭を読んだ僕は、
衝撃を受け、その場で購入し、食い入るように読んだ。
”死すべき定め”
この本は、ハーバード大学医学部・ハーバード大学公衆衛生大学院教授であり、同時に「ニューヨーカー」誌の医学・科学部門のライターも勤めており、
2010年には「タイム」誌で「世界でもっとも影響力のある100人」に選ばれたこともある、外科医アトゥール・ガワンデが書いた本である。
彼が医師として見てきた「人の最期」のいくつかを、具体例を用いて残酷なまでに正確に描写している。
文中でも引用される、小説『エブリマン』でフィリップ・ロスが使った言葉、
”老いは闘いではない。老いは虐殺だ”
は、あながち過言ではないということを思い知らされる。
運動機能は衰え、本を読めないほどの認知症になり、いずれは一人で生きていけなくなる。
そして、それはみなに平等に訪れる。
本書内で著者が訴える「違和感」、
つまり、著者が病院や米国の高齢者施設(ナーシングホーム)で死にゆく患者をみてきて感じていた「違和感」と似たものを、僕も働き始めてから感じてきた。
「果たして、人の最期ってこうあるべきなのか?」
病院で亡くなっていく患者さんの全員とは言わないまでも何割かの人が、
そういった状態で亡くなっていった。
本書でも述べられている通り、病院や高齢者施設で第一となるのは、
「患者の安全」、そして「施設の効率化」だ。
そのために、高齢者は自由を奪われ、プライバシーを奪われ、「自立心」を奪われ、
いずれは、「生きる希望」を失ってしまう。
そんな現状を、圧倒的な文章力、構成力、取材力で書き綴った本書を読むと、
誰もが人の行く末を案じずにはいられなくなる。
だが、
読み進めると「一筋の希望」が見え始める。
彼が経験したいくつかの「理想的な最期」が提示される。
それは、ある末期がんの患者の最期であり、
それは、著者自らの父の最期である。
価値観は人それぞれで、
「何が生きているうちで譲れない条件で、逆に何なら差し出せるのか」
をしっかり確認しないといけない。
抗がん剤を使って3か月余命が伸びるかわりに死ぬまでの6ヶ月を病院で過ごすとしたら、
それは自分にとって価値のあることだろうか。
食べることが出来なくなる代わりに、余命がのびるとしたら?
声が出せなくなる代わりに、致命的となる肺炎が予防できるとしたら?
ある末期がん患者は、その条件をこう表現している。
「もしチョコレートアイスを食べて、フットボールの試合をテレビで見ることが出来るなら、生き延びたいな。それが出来るなら相当な痛みも耐えるし、手術も受ける」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
死にゆく人に今の社会が提供しているものはなんだろう。
安心・安全? いったい誰の?
そして、それって本当に最期に求めることだろうか。
私たちは豊かに生きることに精いっぱいで、
「豊かに死ぬ」ために必要なことを、こんなにも知らない─────
本書の帯の言葉を引用して、この記事を終えようと思う。