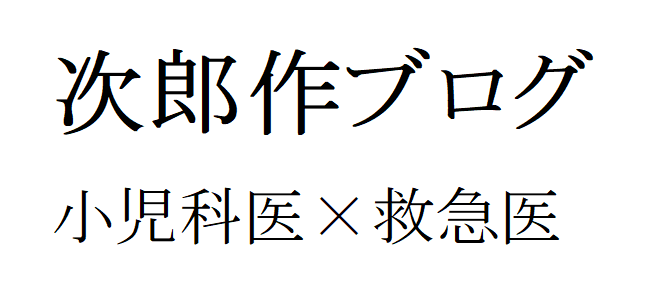目次
1. 【血ガスの伝統的アプローチ】
2. 【血ガスのStewartアプローチ】
3. 【代謝性アシドーシス】
4. 【代謝性アルカローシス】
5. 【低Na血症】
6. 【高Na血症】
7. 【低K血症】
8. 【カルシウムの異常】
9. 【マグネシウムの異常】
10. 【リンの異常】
11. 【DKA糖尿病性ケトアシドーシス】
12. 【アルコール性ケトアシドーシスAKA】
13. 【副腎不全】
14. 【甲状腺クリーゼ】
その他の巻についてもこちらをご覧ください↓
——————————————————————–
【1.血ガスの伝統的アプローチ】
(参考:http://www.osaka-amt.or.jp/lecture/bloodgus/060927.pdf)
①pH≦7.35でアシデミア、pH≧7.45でアルカレミアと判断する。
②pHの変動が呼吸性か代謝性かを確認

・PCO2 =38±2
・HCO3-=24±2
③代償範囲内にあるかどうかを確認

「竜馬先生の血液ガス白熱講義150分」より
・基準値からのズレと、代償の限界値は上記のような比で対応している。
→代償を超えた範囲でのPaCO2の変化あるいはHCO-の変化については、併存する別の酸塩基異常を考える。
→例えば、過換気の呼吸性アルカローシスに対して、HCO3-は低下して急性期代償をするが、下がり幅が上記の比から算出される限界値を超えている場合(HCO3-が限界を超えて下がっている場合)には、背景に代謝性アシドーシスを合併していると考える。
④アニオンギャップ(AG)でアシドーシスの種類を確認

→AG正常の代謝性アシドーシスには生食大量輸液の高Clアシドーシスも含む
AG=Na-Cl-HCO3-
=12±2
ただし、低Alb血症の場合には、補正AG=AG+2.5×(4-Alb)
・様々な代償により、pH, PaCO2, HCO3-が正常値であっても、AGが開大していることがある
→AGが開大している時は、必ず代謝性アシドーシスが存在している。
→その時には、AGの増大分(12との差)、つまりΔAGをHCO3-に足すことで補正HCO3-を求めることが出来る
→真のHCO3-を計算することで、アシドーシスにマスクされた既存のアルカローシスがないかどうかを判断することが出来る。
→ΔAGが高い場合、真のHCO3-が結構高くて、代謝性アルカローシスが隠れていたことが分かるが、代謝性アシドーシスによる低下と釣り合ってしまい、結果的に正常値となってしまっているということ。
→上記の式よりアルブミンが低ければ低いほど補正AGが大きくなり、補正後のHCO3-が高値になることが分かる
→つまり低アルブミン血症により代謝性アルカローシスが惹起されることがわかる。
(腎不全による、慢性のAG開大型代謝性アシドーシスに、嘔吐などの要素が加わり代謝性アルカローシスを合併した場合。このような場合はAGと補正HCO3-を計算しないと真の病態が見えてこない。)
——————————————————————–
【2.血ガスのStewartアプローチ】
(参考:http://www.jseptic.com/journal/115.pdf)
<伝統的アプローチと同じところ>
・陽イオンの総量と陰イオンの総量が生体内で同量であることは両者で共通の大原則。
・HCO3-は単なる緩衝剤であり、「結果として」上昇/低下しているだけである
→HCO3-以外の陰イオンが増える(H+を放出するイオンが増える)とアシドーシスとなる。
→この際、陰イオン全体の総量を保つために、「結果的に」HCO3-が減る
・アシドーシス/アルカローシスを規定するのは陽イオンと陰イオン(HCO3-以外)の差であること。
→この差が大きければ大きいほどアルカローシス、小さければ小さいほどアシドーシスとなる。
→例えば、嘔吐症では、「H+がなくなるからアルカローシス」ではなくて、Cl喪失の結果、上記の差が大きい方に傾くことによってアルカローシスになると考える。
→またメイロン(NaHCO3)の投与は、HCO3-を投与してアルカローシスにするのではなく(そもそも、HCO3-は酸塩基平衡に影響を与えない)、Naを投与することにより、上記の差を大きい方に傾けて、アルカローシスに持っていこうという治療である。
<伝統的アプローチと違うところ>
・伝統的アプローチで「測定されないイオン」として扱われていたイオンを実際に測定することにより、Stewartアプローチでは「測定できるイオン」あるいは「計算できるイオン」へと変更した。
→詳細は図を見ると分かりやすい。
・Stewartアプローチ

(UMA:測定されない陰イオン)
<Stewartアプローチで実際に行うこと>
・Stewartアプローチでは、代謝性の酸塩基異常の原因がどこにあるのかを突き止めるために、陰イオンを
a. 強陰イオン(Cl, Lac)
b. 弱陰イオン(P, Alb)
c. UMA(UnMeasurable Anion)
d. HCO3-
に分けて考える。
・強陰イオン、弱陰イオン、UMA、どの陰イオンが増えてもアシドーシス側へ傾く。
→どの陰イオンが増えたことによる酸塩基異常かが、すなわち病態の理解に結び付く。
・HCO3-の変動は酸塩基異常の原因とはならず、他の陰イオンの動きに合わせて最後に総和の帳尻を合わせるために変動するにすぎないので考えなくてよい。
・陽イオンは全て強イオンとみなす。

①強陰イオンが増える場合
・生理食塩水の大量投与、あるいは高乳酸血症が考えらえる。
→アシドーシスに傾く
→この際、SID(Strong Ion Difference)が縮小する
SID≒Na-Cl
(正常値38mEq/L)
→つまりSIDが38以下なら強陰イオンアシドーシス、38以上なら強陰イオンアルカローシスと考える
→アルカローシスはこの逆
②弱陰イオンが増える場合
・高P血症、高Alb血症が考えられる。
→アシドーシスに傾く
→それぞれ、正常値よりも高ければアシドーシスに、低ければアルカローシスに傾く。
→頻度から言うと、低Albや低Pのアルカローシスが多い。
→腎不全患者の高Pによりアシドーシスとなる場合も想定される。
③UMAが増える場合
・原因はケトアシドーシス、メタノール、アスピリン負荷、エチレングリコールなどさまざまある。
・重症患者において、死亡リスクの推定に役立ったとされる。
・(私見)強陰イオン上昇による病態と、UMA上昇による病態は合併しうるものと考える。
→体内で起きている現象もoverlapしているものと考える。
UMA=Na+K-Cl-HCO3-2×Alb-0.5×P
(正常値は0)
——————————————————————–
【3.代謝性アシドーシス】
・Stewartアプローチによる病態の類推に加え、伝統的アプローチによる一般的なアシドーシスには下記のようなものがある。


http://www.osaka-amt.or.jp/lecture/bloodgus/060927.pdf
[敗血症性ショックと乳酸]
・ショック患者では、組織低酸素が起きている
・敗血症性ショック患者では乳酸が高値となる。
→しかし乳酸高値は低酸素部位での嫌気性代謝を反映しているものではない。
→組織低酸素or組織低灌流と高乳酸血症の間には関連性がない。
・ただし、機序こそ不明ではあるが、重症化の結果として上昇することは確かであり、予後予測や治療指標に用いることができるのは確かである。
[代謝性アシドーシスとカテコラミン不応]
・代謝性アシドーシスでは心収縮力の低下などが起きる可能性がある
・さらに代謝性アシドーシスにより、カテコラミンの効果が得られづらくなる可能性が古くから考えられているが、人間での検証はされていない。
・動物実験では、呼吸性アルカローシスによるpH低下ではカテコラミン不応が起きなかったことから、代謝性アシドーシスに伴ってカテコラミン不応が起きている可能性がある。
[代謝性アシドーシスとメイロン]
・乳酸アシドーシスやケトアシドーシスなどの病態にメイロンを投与することは、有害である可能性がある。
→ただしpH6.9を下回る重症アシドーシスに対しては、50mL/minでのメイロン投与を考慮する。Wolfsdorf J, et al. 2006;29(5):1150-9
→投与量の目安はBE×10mL
(ただし体重42kgでの換算)
——————————————————————–
【4.代謝性アルカローシス】
・代謝性アルカローシスはICUで最も多く認められる酸塩基平衡異常である。
・アルカローシスの形成因子(原疾患にあたる)と維持因子(循環血漿量減少、低K、腎機能障害にあたる)に分けて考える。
→治療自体も個別に行う必要がある。
・重症の代謝性アルカローシス(pH>7.55)の死亡率は45%と高値であるにもかかわらず、特徴的な症状が認められず見逃されやすい。
・代謝性アルカローシスの原因はまずは、嘔吐と利尿剤
[代謝性アルカローシスの病態]
①形成因子と維持因子




→尿中ClはCl欠乏の有無を容易に評価できる検査である。
[代謝性アルカローシスの症状と治療介入]
<症状>
・治療で最初に考えるのは、緊急介入を要するpH>7.6の重症アルカレミアの確認である。
・pH>7.6で死亡率80%。
・呼吸性よりも代謝性アルカローシスのほうが死亡率を上げる。

<治療>
・原因がはっきりしている場合(嘔吐や利尿剤など)は原則的にそれに対する治療を行う。
その他、
①循環血漿量とClの補充
→生食を100mL/hr程度で投与
→Clの補正量は0.2x体重x(100-血清Cl) mEqで計算する。
→体液過剰の病態がある場合にはKClで同量のClを投与する。
→代謝性アルカローシスにともなう低Kの治療にもなる。
②スピロノラクトン
・Cl排出型ないし鉱質コルチコイド過剰によるアルカローシス
・低K血症が認められる場合
③アセタゾラミド(ダイアモックス)
・代謝性アルカローシスでCre<4mg/dLである場合には投与を考慮する。
・250mg-500mg/dayで
→ただし、過剰投与の場合には低K血症を伴う代謝性アシドーシスにおちいる。
——————————————————————–
【5.低Na血症】
(参考:https://www.igaku.co.jp/pdf/resident0904-4.pdf)
・大原則として、どの電解質においても、低値を取る場合は3つのルートに分けて考えると考えやすい。
①細胞内シフト
②腎外(腸管など)喪失
③腎喪失
・低Na血症の本態は、体内のNa総量と比較して相対的に水の量が過剰にある低張性低Na血症である。
・等張性低Na血症や高張性高Na血症を最初に除外したあとに、低張性低Na血症の鑑別にすすむという考え方がシンプルで良い。
・低張性低Na血症は重症度、発症の急性/慢性、細胞外液量の多寡などによって分類される。
→慢性低Na血症を急激に補正するとODS(浸透圧性脱髄症候群)に陥るため、どちらかの判断がつかない場合には、慢性低Na血症と考えて補正する。
[低Na血症の分類]
①濃度
軽度:130-135
中等度:125-129
重度:<125
②発症時間
急性:48時間未満
慢性:48時間以上
③症状
中等症:嘔吐なしの悪心、混乱、頭痛
重症:嘔吐、循環呼吸の障害、傾眠、痙攣、GCS<8
[低Na血症の原因診断]
①高張性・等張性低Na血症の除外
・高血糖、マンニトール、極端な高脂血症/高タンパク血症の場合、低Na血症を呈する。
・アルゴリズムのポイントは
a. 急性または重度の症状を呈する場合には、脳浮腫のリスクが高いため、診断よりも補正による治療を優先すること
b. 細胞外液量の推定は診断感度・特異度ともに低いことから、アルゴリズムの上流には置かない
→尿浸透圧と尿中Na濃度をより上流で用いた方が精度が高い。
c. 診断がつかない場合、もしくは診断に基づいて治療をしても低Na血症が続く場合は、再評価を行うことや、専門家へのコンサルトをためらわないことが重要である。
[低Na血症診断の指標]
①尿浸透圧は(尿比重の下2桁)×25~40で概算される。
→尿浸透圧>血症浸透圧の際には薬物の副作用によるSIADを疑う
②細胞外液量、正常or 減少の判断
・身体所見は感度/特異度ともに診断能は不十分である。
a. FEUAを用いる
→利尿剤や尿量に影響を受けない。
→FEUA>12%でSIADHの診断感度86% 特異度100%
→つまりFEUA>12%であれば細胞外液量正常、<12%であれば細胞外液量減少
b. 尿量、FENa、FEureaを用いる
ⅰ. 尿量が多い場合(Ucre/Pcre<140)
→FeNa>0.5% または FEurea>55% でSIADHの診断
ⅱ. 尿量が少ない場合(Ucre/Pcre>140)
→FeNa>0.15% または FEurea>45% でSIADHの診断
[低Na血症の治療]
・重症の場合には、3%食塩水を投与
→中等症でも投与を考慮する。
→150mLを20分で投与
・3%食塩水はNS400mL + 10%NaCl 6A/120mL=520mL
で作る。
・3%食塩水を作る暇がない時は、メイロンを6%食塩水と同等とみなして使用する
・補正は10mEq/L/24hrと18mEq/L/48hrを超えないようにする
→これを超えるとODSのリスクが高まる。


[低Na血症治療のQuestion]
<低Na血症の発症は急性or慢性?>
①血清Na濃度の低下が急速(48hr以内)かつ重度に起こる場合、脳浮腫のリスクが高い。
→急速に補正
②発症より48hr以上経った慢性の低Na血症の急速補正はODSのリスクとなる。
→急速な補正はしない。
→発症時間が不明な場合にもODSを防ぐ意味で、慢性として扱う。
<なぜNaClは3%?>
・SIADHのように、ADHが過剰に分泌されている状態では、アルドステロンの分泌が抑制されており、尿Na排泄が亢進している。
→たとえ生理食塩水(Na 154mEq/L)を投与しても、Naが尿中に排泄される結果、自由水のみが体内に再吸収され(尿浸透圧上昇)、結果的に血清Na濃度は低下することになる。
→3% Naclでは血清Naを下げるまでに自由水を大量に再吸収するためには、尿浸透圧が理論上1000以上になる必要があり、これは実際にここまで上昇することはなく、結果的に速やかに血清Na濃度の上昇が得られる。
<Na補正のΔNaはどのように予想する?>
・ΔNa=(輸液Na+輸液K-血清Na)/(体内総水分量+1)
・体内総水分量=0.5×体重
→当然誤差はある。
<水制限の実際は?>
・SIADHに対しては大きな合併症もなく安全に行うことが出来る。
・くも膜下出血後の低Na血症に対しては水制限を行うことで脳梗塞が高率で起こり得る。
・水制限の量は、尿/血症浸透圧比(U/P比)を用いて決定する
→U/P比=(尿Na+尿K)/血清Na
①U/P>1の場合
・尿が排泄されるたびに電解質の方が自由水よりも排泄される状態である。
→尿量は少なくしたい
→飲水制限500mL/day程度に設定。
②U/P<1の場合
・尿には自由水の方が電解質よりも多く排泄されている。
・自由水の摂取は、尿中自由水+不感蒸泄量よりも少なければよい。
→1000mL/day程度で良い
<低Na血症は利尿薬で補正可能?>
①ループ利尿薬
Na,Clの再吸収を阻害することにより、水の再吸収を阻害する。
→結果として血清Naは上昇する。
→SIADHに対して水制限のみで治療が難渋する場合にはループ利尿薬の投与が考慮される。
→ただし、脱水予防および脱水に伴うADH分泌刺激えお抑える目的で経口塩化ナトリウムを併用する。
②トルバプタン(サムスカ)
・血清Na濃度は上昇する
・死亡率低下はない
・合併症や重度の副作用増加はない。ODSもない
・血清Naの急速な上昇リスクはある。
→有用な可能性はあるが、保険適用外使用であり、どのような状況がベストかなどは定まっていない。
<過剰補正が起こりやすい低Na血症はなにか>
①心因性多飲
②細胞外液量減少性低Na血症
→補液による循環血液量回復により、ADHの分泌が停止する。
③一過性のADH分泌によった低Na血症
→原因薬物の中止や術後、疼痛の改善によりADH分泌が抑制される。
④並行した治療がある場合
→K補充や透析中はNa補正が過剰になりやすい
・血清Naの上昇の程度が適切であっても、急に尿量の増加がみられる場合には途中で低Na血症の原因が改善し水利尿が起こっていることを疑い、その後の急激なNaの上昇を警戒する。
→血清Na濃度の補正速度が過剰となった場合には、迅速な逆補正を行うことが推奨されている。
→Na投与を中止か遅らせたうえで、自由水(5% ブドウ糖水10mL/kg/hr)を負荷する。
→さらにデスモプレシン2μgを8時間ごとの投与を検討する。
<ODSの臨床像とは?>
①危険因子
肝硬変、アルコール乱用、栄養障害、低K血症、腎不全/透析
→血清Naの濃度が正常でもODSを起こし得る。
→Naの補正が緩徐で起きうる。
②診断
意識変容、進行する対麻痺/四肢麻痺、痙攣、嚥下障害、構音障害、眼球運動障害などの症状で疑う。
→低Na血症による症状から、新たに神経学的症状が出現した場合に疑う。
→MRIを撮影する。
③神経学的予後
急激なNa補正によりODSを発症したとしても、逆補正により血清Na濃度を下げることにより、症状が改善または消失した症例もあり、可逆的な病態であることも十分予想される。
——————————————————————–
【6.高Na血症】
・健常人では口渇感による水分摂取と、ADH分泌刺激により、高Na血症はおきづらい
・反対にICU領域の患者は鎮静/挿管されていたりと、高Na血症をきたしやすい
[高Na血症の原因診断]
・高Na血症は、総体内Na量の増加あるいは、体内総水分量の減少により起きるため、この二つに分けて考えるのが良い。

①総体内Na量の増加
Naの過剰摂取、高張食塩液、生理食塩水、メイロン投与、Naを多く含んだ抗菌薬投与
②総体内水分量の減少
・腎性喪失/腎外性喪失の2種類がある。
→簡便な鑑別方法としては、尿浸透圧を測定する
→あるいは簡易EFWC用いて
腎外性:(尿Na+尿K)/血清Na>1
腎性 :(尿Na+尿K)/血清Na<1
でも良い。
・血管内volumeの評価は概して容易でなく(時に正確な評価は不可能で)、診断プロトコルの上位に置かないことになっている。

・尿崩症は
a. 多尿>3L/day
b. 血清Na濃度上昇
c. 尿浸透圧<血清浸透圧
(中枢性尿崩症では<200, 腎性尿崩症では200~500となる)
により診断される。
・尿崩症が原因となるのは内科領域では4%程度であり、多くは利尿薬の投与やNa過剰の輸液など、医原性の原因となっていた。
[高Na血症の補正]
・145mEqを超えないようにマネージメントを行う。
・補正のポイントは
①慢性発症の高Naを急激に補正すると脳ヘルニアが生じる。
②血管内volumeが減少している場合には、まず晶質液による輸液蘇生を行う。
③自由水の投与量の目安は
Water deficit
=体重×0.5×(血清Na/140 - 1)
で求める。
④過剰補正に対しては、Na投与による逆補正を行う。

[高Na血症治療のQuestion]
<浮腫で除水したい場合の高Naをどうするか>
・血管内volumeと間質浮腫の存在は直接的な関連はない。
・まず、臨床上のプロブレムをきたさない浮腫については、治療の対象とは考えない。
→栄養やリハビリの介入により自然に除水される。
→例えば、敗血症などによる血管外漏出で血管内容量減少があるが高Na血症と浮腫がある場合、浮腫があるからといって除水を行うのは安易である。
→自由水投与による高Na補正を行う。
→安定期(利尿期)に入り、フロセミドを使う場合においても、適宜自由水の投与を行いながら、利尿を続ける。
<頭蓋内圧亢進と治療的高Na血症>
・脳梗塞患者においては、細胞毒性浮腫によりほぼ前例で脳浮腫が起こるため、低張液(細胞内液よりも浸透圧の低い輸液、1号液や3号液など)を避けるべきである。
・では逆に、高張液の予防投与により、積極的に細胞内液を間質へ移動させる治療にエビデンスはあるのだろうか
→エビデンス乏しい。
・結局、脱水や低張液を避けるのは当然として、血液希釈や予防的高張液投与を支持するエビデンスに乏しいことを考えると、脳梗塞患者への輸液の基本は等張液(細胞外液)によるeuvolemia管理であると考えらえる。
・脳梗塞患者の脳浮腫に対して、高張液の使用が臨床的転帰に与える影響について調べた質の高い研究はほとんどない。
→しかしながら、AHAなどのガイドラインにおいても、エビデンスレベルは低いものの、マンニトールによる浸透圧利尿や高張食塩液の使用が推奨されている。
→あくまでも開頭減圧術施行までの一時的治療との位置づけとなる。
・アルブミンに脳浮腫を軽減し、微小循環を改善させる効果が期待されALIAS studyが実施された。
→25%アルブミンの投与群で90日後の神経学的予後に有意差なし
→25%アルブミンの投与群で症候性頭蓋内出血、肺水腫・うっ血性心不全の発生率が有意に高かった。
→現状、脳梗塞患者に対して神経保護作用を期待しての高容量アルブミンは投与してはいけないと考える。
<マンニトールの投与方法は?>
・目標血清Na濃度を145~155mEq/Lに設定する
・マンニトール0.25~1g/kgをボーラス投与し、2-6時間ごとに反復投与可能
・BBB内外における浸透圧の差によって水分を血管内へシフトさせることで頭蓋内圧を低下させる。
・日本ではマンニトールよりもグリセロールが優先的に用いられている。
→海外ではマンニトールが主流。グリセロールは古い薬。
・高浸透圧食塩水でもマンニトールに劣らない頭蓋内圧低下作用があるというエビデンスが出てきている。さらに安価で、副作用が少ないことも示されている。
——————————————————————–
【7.低K血症】
・Kの血中濃度調節は
①細胞内外の移動
②腎からの排泄
③腸管からの排泄
の3つの機構により行われている。
・急性調節機構として、高K血症に対して①細胞内シフトが起きる。
・慢性調節機構として②③の腎・腸管からの排泄が起こる。
・平常時には腎から排泄が主要な排泄経路となっている。
→K摂取不足により有意な低K血症が発生するには数週間~数か月の飢餓状態が必要であり、ICUではほとんどみかけない。
[低K血症の病歴]
・嘔吐、下痢、利尿薬の長期使用がないかどうかを確認。
・急性経過(24hr以内)の低K血症がある場合には、細胞内シフトの要因がないかどうか。
→アルカレミア、インスリン、β2アゴニスト、甲状腺ホルモン、低体温
[尿中K、酸塩基平衡の評価]
・病歴から要因が分からない場合には尿中K排泄と酸塩基平衡の評価を行う。
・尿中K排泄の指標は
①TTKG(ただし、尿浸透圧>血症浸透圧の状況でのみ信頼性あり)
②尿中K/Cr(ただし、やせた患者ではCrが低く値を過大評価してしまう)
を用いる。
・下痢、嘔吐に関しては、腎性喪失様の検査結果を呈することがあるが、症状から明らかであれば、気にしない。

[心血管疾患における適正K濃度]
・AMI入院患者のKは3.5~4.5mEq/Lで管理すべきであり、それ以上でもそれ以下でも良くない。
・心不全では4.0~5.5mEq/Lとの報告がある。
→低値を補正するためには、スピロノラクトンを用いる方が良いとされている。
[肝不全における適正K濃度]
・低K血症では近位尿細管でのアンモニア産生が亢進する。
→肝不全で肝性脳症がある場合にはK>3mEq/Lに保つ
[補正の実際]
a. 製剤
・リン酸カリウム、グルコン酸カリウム、アスパラギン酸カリウム
→細胞内液に取り込まれやすく、代謝性アシドーシスの合併例や細胞内のK不足が疑わしい場合にのみ有効である。
・塩化カリウム
→細胞外液に分布しやすく、細胞外K濃度の上昇に寄与しやすい。
→基本的にこちらを用いる。
→塩化カリウムの経口製剤は静脈内投与と比べてもそれほどKの上昇が遅くないため、大量投与時には積極的に用いる。
→ただし投与後の細胞内シフトにより、上昇は一時的
(注射剤は、高濃度高速投与が出来ない。)
b. 速度と濃度
・添付文書上は、40mEq/Lをこえない濃度、かつ20mEq/hrを超えない速度でとなっている。
→高K血症による致死的不整脈や、静脈炎を防ぐため
(私見)
→これは、最も急速な補正でもNS500mL+KCl 20mEq/Lを1時間で投与するのが限界である
→volume管理上、あまり現実的でない
→中心静脈を使用したこれ以上の濃度や速度での補正は各施設基準によるところが大きい。
[低K血症後のリバウンド高K血症]
・細胞内シフトによる低K血症に対して、K補充を行った後に、病態改善に伴ってKが細胞外に戻ってくると高K血症を呈することがある。
→ただし低体温療法のよる低K血症にたいしては、3.0mEq/Lを保つように管理した後に復温しても、リバウンド高K血症は生じなかった。
→甲状腺機能亢進症に伴う周期性四肢麻痺に対しては、K補充を行うことによってその後のリバウンド高K血症が生じ、致死的な経過を辿った症例報告がある。
→甲状腺機能亢進に伴う周期性四肢麻痺に対しては、β2遮断薬(インデラル/プロプラノロール)によりKの補正が可能である可能性がある。
——————————————————————–
【8.カルシウムの異常】
・血中のCa濃度は副甲状腺ホルモン(PTH)とビタミンDにより制御されている。
→PTHは細胞外液中のCa濃度を上げ、P濃度を下げる
→ビタミンDは細胞外液中のCa、Pどちらの濃度も上げる。
・高Ca血症の症状として、筋力低下・悪心・無気力・見当識障害・食思不振などがあるが非特異的な症状である。
・アルブミンによる補正Caは信頼性に欠けるとの報告があり、可能な限り、イオン化Caで評価を行うのが良い。
[高Ca血症の原因診断]
・その大半は、原発性副甲状腺機能亢進症+悪性腫瘍+カルシウム/ビタミンD製剤の内服で説明がつく。
・その他、長期臥床によるもの、重症疾患/腎機能障害からの回復期に高Ca血症がみられることがある。
→まずはこれらの詳細な病歴聴取や原因薬剤の検索を行う。

→PTHintactの値は、絶対値で判断するのは困難であり、疾患ごとに相対的な判断が求められる。
[高Ca血症の治療]
・11.5mg/dL以下では通常無症候性であり、直ちに治療介入する必要はない。
・一般的に用いられる高Ca血症の治療として
①輸液療法
②カルシトニン
③ビスホスホネート
などが挙げられる。
①輸液療法
・投与療法は高Ca血症の程度や、年齢、基礎疾患などによって異なるが、3-6L/dayの大量輸液が必要となるケースもある。
②カルシトニン
・高Ca血症の原因によらず治療に使用できる
→4-6hrで効果が発現し、Caを1-2mg/dL低下させる。
→輸液療法とともに初期治療に用いるのが効果的である。
③ビスホスホネート
・Caを低下させる効果が発現するまでに2-6日かかる
・投与中の歯科治療で顎骨壊死をきたすことがあり、投与前に口腔内チェックを行い、治療終了後に投与する。
・生殖年齢の女性に対しては慎重に適応を判断する。
→骨に沈着し、妊娠中にも継続的にBP製剤が胎盤を通して沈着する。

[低Ca血症の鑑別]
・低Ca血症によりPTHが正常反応により高値なのか
・PTHが分泌できない(低値)ため、低Ca血症なのか
これらの判断から鑑別が始まる。

[低Ca血症の治療]
・軽度で慢性であれば無症候である。
・症状としては手足攣縮、テタニー、痙攣、不整脈へと進展する。
・Ca<7.5mg/dLでは静脈内投与による補正を検討する。
→それ以外では経口Ca製剤やビタミンD製剤の投与を検討する。

・グルコン酸カルシウムは日本では1A=8.5% 5mLが一般的
・持続投与は
10%グルコン酸Ca 100mL/10A + NS/5%Glu 500mLを50mL/hrから投与開始し、4hrごとに投与速度を見直す。
→正常値上加減の値を目標とする。
・大量輸血時には抗凝固薬として含まれるクエン酸ナトリウムにより、低Ca血症が生じる
→グルコン酸カルシウムの投与を行う
→100mL/hrを超える投与に対して、500mLの輸血ごとに、8.5%カルチコール1Aを投与
(投与量の文献はあまりないため、参考程度)
——————————————————————–
【9.マグネシウムの異常】
[体内Mgの居場所]
・体内のMgの99%は細胞内にあり、血清中にはわずか0.3%が存在するのみである。
→さらに血清Mgの67%はイオンとして存在し、その他は他の分子と結合した形で存在する。
→検査室ではこれら血清Mgの分画のすべてを足した濃度を測定している。
[Mg欠乏の指標]
・Mgの欠乏が起こった場合、尿中へのMg排泄は減少し、当初は血清Mgが正常に保たれる
→つまり血清Mgが正常値でも、Mg欠乏の病態が起きうるということ。
→さらに、輸液による希釈や細胞内シフトの影響を考えると、血清Mgや血清イオンMgがMg欠乏を正確に評価できていない可能性が考えられる。
<尿中Mg測定の有用性>
・腎機能正常が前提ではあるが、Mg欠乏の初期に尿中Mg排泄が代償性に減少する。
・FEMgの測定により、喪失経路の推定に役立つ。
FEMg = 尿Mg×血清Cr/血清Mg×尿Cr×0.7
[Mg欠乏の症状]
・有症状の際には、血清Mgが正常値でも(それが真の指標ではないので)、積極的にMg欠乏を疑う。
→特に低栄養状態、利尿薬使用、嘔吐下痢、慢性肝疾患の患者ではMgが欠乏していても血清Mgが正常値をとりうる。

——————————————————————–
【10.リンの異常】
・ICU領域の低P血症発症率は30%にもなる
→敗血症で70%, 熱傷、飢餓状態では100%となる。
・P<1.0mg/dlを下回る重度の低P血症は重篤な症状や死亡につながる。
[低P血症の原因]
①細胞内シフト
・インスリン分泌による細胞外→細胞内シフト
(Kと一緒)
・呼吸性アルカローシスによるCO2の細胞内濃度低下に伴って、細胞内pHを上昇させるために、Pが細胞内シフトする。
→敗血症、呼吸器疾患、アスピリン中毒
・カテコラミン分泌、悪性腫瘍に伴ってPが細胞内に取り込まれる。
・飢餓状態、Refeeding SyndromeなどでPが細胞内シフトする。
②Pの摂取不足、腎外排出亢進
→P制限食、腸管からのP分泌亢進、消化管術後、吸収不良症候群
③腎からの喪失
・利尿薬
・感染などによる間質性腎炎、尿細管障害
→NGALやNAG、などのマーカ―が有用
④代謝性疾患
・原発性甲状腺機能亢進症
→Caは上昇、Pは低下
・ビタミンD低下
→Caは低下、Pも低下


[低P血症の症状]

→低P血症の呼吸筋低下により、人工呼吸器離脱遅延が起きる
→低P血症の心筋収縮力低下により、VTなどの不整脈が増えるとされる。
[低P血症の補正方法]
・最重症(P<1.0)では20mmol/hrまで投与可能
・中等度(1<P<2)であれば、6時間かけてリン酸ナトリウム1A(20mmol)を投与
→経口補正する場合には、経静脈的投与の場合の3倍量を投与
[Refeeding Syndrome]
a. 病態
・種々の要因で栄養不良になった状態の患者に人工的に栄養を投与した結果、細胞内への水分移動と電解質移動に伴い、症状を起こす疾患群
・栄養の再開により、インスリン分泌の増強、その他の要因により、細胞内でP,K,Mgの需要が急激に高まり、細胞内シフトを引き起こす。
・電解質異常の他にも、肝酵素逸脱を引き起こす。
c. 治療
・極めて重度のリスク群
→5kcl/kg/dayから開始
・重度のリスク群
→10kcl/kg/dayから開始
・中等度のリスク群
→20kcl/kg/dayから開始
・4-7日をかけて必要カロリーまで漸増させていく。
——————————————————————–
【11.DKA糖尿病性ケトアシドーシス】
[参考]
・考えるERサムライプラクティス2014
・研修医当直御法度
・up to date
[CQ1]
DKA患者のアピアランスはどのようなものか。
[A1]
以下に典型例を示す
![]()
(http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03161_03)
・呼気は甘く、腐ったリンゴのようなにおい
・呼吸数は必ずしも頻呼吸とはならない
→代謝性アシドーシスを呼吸性代償するために、規則的で持続性の深呼吸(Kussmaul呼吸)
[CQ2]
DKAの診断のために何の検査をして、何の数値を読む?
[A2]
腹痛+嘔吐+Kussmaul呼吸±糖尿病の既往
→条件反射で動脈血ガス
ちなみに

<診断基準>
①血糖値>250mg/dL
②アシドーシス(pH<7.30, HCO3-<18)
③ケトーシス(尿ケトンor血中ケトン陽性)
→尿ケトンは陰性のこともある。

[CQ3]
DKAの病態は?HHSの病態は?
[A3]


http://www.matsuyama.jrc.or.jp/rinsyo/news/wp-content/uploads/2013/02/6bb769ccc724b0122a00664a501de3ff.pdf
・二つの病態は
①DKAはインスリンの絶対的欠乏によるケトーシスがメイン
②HHSはインスリンの相対的欠乏による高度脱水がメイン
という点で差別化される。
→もちろんこの病態はoverlapすることもある。
→ただし初療において、治療方針に大きな差はなく、鑑別は必須ではない
・脱水の程度は
①DKAで3-6L
②HHSで8-10L
といわれる。
・DKAにおいては、特に脂肪酸の分解によるアシドーシス進行を止めることが治療の本質であって、血糖値を下げることが治療ではない(あるいは、別の言い方をすると、血糖値の低下が直接アシドーシスの改善を意味するものではない)
・それゆえ、血糖値の低下をもってインスリンを急に止めるのは半ば禁忌に近いものと考えられる。
[CQ4]
DKA,HHS治療の一本目の柱は何か
[A4]
輸液療法
http://www.jseptic.com/rinsho/questionnaire55.pdf
→武居/則末先生の回答参照
①製剤
・生食による高Clアシドーシスを避ける意味でも乳酸リンゲルで良さそう。
・ただし、DKA治療をするうえでは、大量輸液に伴う脳浮腫の発現を防がなければならない
→脳浮腫や肺水腫の発現の際には、血漿浸透圧の低下が重要な関連因子となっている可能性がある
→輸液の際に、維持液などの低張液を用いるべきではない。
→また輸液をしながらNaの濃度もモニタリングし、Naを低下させないような管理が重要である。
②投与量
心機能を評価したうえで、500-1000mL/hrで開始。
最初の1時間で1000mLを入れてしまっても良い。
→その後は身体所見や血糖の降下具合、AGが開大していかないかを見ながら適宜輸液量を調節していく。
→輸液量の目安はDKAで体重の5%, HHSで7.5%(則末論)

③外液→維持液への変更
血糖値が下がってきたら(DKAで250mg/dL, HHSで300mg/dL)、ブドウ糖入りの維持輸液へ変更する
→3号液+10%NaCl 20ml 1Aが最適解か
→血糖が下がってきても、インスリン投与を急に止めるとDKAへ逆戻りする。
→これは、つまり、脂肪酸の分解を止めるだけの十分なグリコーゲンが体内にまだ貯蓄されていないことを示す
→そのため、グルコースとインスリンを同時に投与することにより、解糖系をしっかり回して体内の糖貯蓄を作ってあげることで、脂肪酸の分解を止める必要がある。
[CQ5]
DKA,HHS治療の二本目の柱は何か
[A5]
インスリン療法
①開始のタイミング
→輸液と同時に開始で良い?
→脱水の状態で血糖を下げるとショックになるため、輸液のloadingが済んでからがよい?
→いずれにしても、「高血糖であること」自体には焦らなくてよい。
②調節方法
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5468371/
ⅰ. インスリン50単位(0.5mL)+生食49.5mL
→1mL/1Uに医師が調剤し、0.14U/kg/hrで持続投与開始
→最初のボーラス投与は必要なし(脳浮腫助長するかもしれないので)
ⅱ. 血糖の下げ幅は最初の1時間で50-70mg/dl、治療開始前血糖の10%などの指標がある。
→下がらなかったら、0.14U/kgをボーラス投与。
→持続投与の速度は0.14U/kg/hrのまま
ⅲ. 血糖値が250-300mg/dL(pH>7.3, HCO3->15やAG<12なども指標に)まで下がったら、0.02-0.05U/kg/hrに一気に減量し、血糖値を現状維持できるようにする。上記のようにブドウ糖の投与とインスリンの投与を同時に行うようにしつつ、次第にインスリンの皮下投与をoverlapさせながら持続投与の終了を目指す。
→持続投与終了間際6時間の投与速度を平均し1時間必要量を算出。それに24を掛けることで持続効果型インスリン(グラルギン)の1日必要量を計算。
→皮下注実施2時間後に、持続投与を終了。
Schmeltz et al. Endocr Pract (2007) 12(6):641–50.10.4158/EP.12.6.641

[CQ6]
DKA,HHS治療の三本目の柱は何か
[A6]
カリウム補正

[CQ7]
DKA治療四本目の柱は何か
[A6]
pH>6.9ではメイロンによる積極的な補正は推奨されない。
pH<6.9でメイロンによるアシドーシス補正
→メイロン50mL/hrで投与する
Wolfsdorf J, et al. 2006;29(5):1150-9
↑下の文献を参照し6.9というMagic numberを記載したアメリカの学会
Ann Intern Med 106 : 615 –618,1987
↑アシドーシスで心収縮下がる・血管拡張するなどの元文献
[CQ8]
DKAの誘因はなにか
[A8]
・もっとも頻度が高いのは、感染症である
→生体ストレスにより血糖上昇し、インスリン必要量が増えている病態を考える。
・病識の乏しい患者のインスリンコンプライアンス不足でも起きる。
・その他、5Iにより覚える。

https://www.m3.com/open/clinical/news/article/544868/
——————————————————————–
【12.アルコール性ケトアシドーシスAKA】
[背景]
・日常の臨床で遭遇するケトアシドーシスは多くがDKAであるが、実はアルコールによるケトアシドーシスも稀ではない。
・慢性アルコール依存患者は容易にケトーシスやケトアシドーシスに傾きやすい。
・救急外来でpH<7.0となるような高度アシドーシスのなかで、最も多いのがAKAであった(著者施設)
→心停止に至り、死亡する例も決して珍しくない
[病態]
・以下の3つに分ける
①栄養障害
②慢性的なアルコール摂取
③脱水
→循環血漿量は著しく低下しており、循環血症量減少がストレスホルモンを増加させ、血中遊離脂肪酸の増加を介してケトーシスへ傾かせる。
・アルコール依存患者の酸塩基異常は様々な要因が混ざり合っており、非常に複雑である。
①ケトアシドーシス
②アルコール依存患者の乳酸アシドーシス
→肝臓における慢性的な乳酸産生亢進
③アルコール性肝障害、ビタミンB1欠乏、痙攣による乳酸増加
④嘔吐、過換気によるアルカローシス
これらの要素をはらんでいるため、その正確な把握は難しい。
[診断]
・明確な診断基準は存在しない
・典型的な大酒家の病歴、臨床所見、AG開大した代謝性アシドーシスのみでAKAの診断を考えなくてはならない。
①臨床経過からの診断
→アルコール依存であることが大前提
→腹痛や嘔吐により飲酒が出来なくなった状態で搬送されることが多い
→急性膵炎や消化管出血により腹痛・嘔吐が生じ、その後二次的にケトアシドーシスを生じることもある、
②血ガス所見
→AG開大性の代謝性アシドーシス
→高乳酸値を呈することも少なくないが、乳酸増加のみでは代謝性アシドーシスを説明できないことでAKAを疑う。
→血糖値は正常であることでDKAやHHSからの鑑別ポイントである。
→血糖値正常のAG開大型ケトアシドーシスを見たらAKAを疑う。
(ただしDM合併のAKAなどはさらに鑑別が困難となる)
[治療]
・血糖値は正常であり、かつインスリンの投与は低P血症を助長するため行わない
・基本的な治療方針は輸液と電解質管理である。
→特に、栄養障害の観点から低P血症を併発している、または出現することが多いため、留意する。
→K,Mgなども同様である
→Refeeding Syndromeに注意
・VitB12の補充も忘れずに行う。

・また、急性膵炎や消化管出血などの併存症が二次的にアシドーシスをきたしていないかどうか、検索する。
——————————————————————–
【13.副腎不全】
・副腎不全は視床下部(三次性)、下垂体(二次性)、副腎(原発性)のいずれかが障害されることで、コルチゾールの分泌が障害される病態である
・原発性副腎不全ではコルチゾール以外にも、アルドステロンも低下する。
・特異的な所見に乏しく、診断は難しい。
→重症疾患管理では常に副腎不全の合併を疑いながら診療する。
[原因]
・原発性副腎不全は自己免疫性副腎不全が全体の70-90%を占める。
→その他、悪性腫瘍、感染症が原因となる。
・二次性副腎不全は下垂体機能低下により起きる
→下垂体腫瘍、自己免疫性下垂体炎(リンパ球性、IgG4関連)
→Sheehan症候群、頭部外傷、髄膜炎
・三次性副腎不全は視床下部機能障害が原因となる
→長期的なステロイド投与による副腎不全はこちらに分類される。
[症状、身体所見、検査]
・副腎不全には特異的な症状が少ないため、疑わないと診断出来ない。
・症状は下記の表のとおりである。

→1/4の例で仕事を退職しており、1/3の例で仕事内容が変化している。
→原因がはっきりしない不定愁訴や上述の非特異的症状、気分障害、生活変化がある患者では疑う必要がある
→内分泌疾患は、嘔吐下痢などの非特異的症状、不定愁訴、気分障害などで受診することがあるので、精神病患者などと決めつけないことが大事である。
[原発性と二次性の違い]
・原発性ではACTH上昇→皮膚・歯肉の色素沈着
・二次性ではACTH低下→皮膚蒼白
・原発性では低Na、低Kが多い
・二次性では電解質異常はそれほど多くない
・原発性では、アルドステロン欠乏により、塩分を渇望する
・二次性では、他の下垂体ホルモン異常との合併があり高PRLによる乳汁分泌、中枢性尿崩症、月経不順、下垂体腫大による両耳側半盲が起きうる。
[副腎クリーゼ]
・慢性副腎不全患者に感染症・発熱、ステロイド中断、手術、運動などの侵襲が起こった場合に発症する。
→急激なコルチゾール欠乏が起き、低血圧・ショック・意識障害の状態となる。
→病歴聴取が重要となる。
・副腎不全のリスクがる患者での悪心・嘔吐、意識障害、発熱などで疑う。
・補液治療やカテコラミンに不応の低血圧で副腎不全を疑う。
・重症患者でも抑制されない好酸球(2-3%)
→通常は抑制される。
<重症患者での副腎不全>
a. 病態
・急性疾患、外傷、手術侵襲などのストレスに対してコルチゾールの分泌亢進、代謝遅延により、組織濃度は高く保たれる
・一方で重症疾患患者では、上記の分泌に伴う枯渇や受容体のダウンレギュレーションにより分泌低下、作用低下が生じ、副腎不全(CIRCI)に陥る。
→敗血症ではCIRCIの頻度は60%であった。
・CIRCIでは原発性・二次性・三次性すべての要素が関連している
b. 診断
・随時コルチゾールが参考となる
①コルチゾール<15μg →CIRCI ②コルチゾール>34μg
→副腎機能正常
③15μg<コルチゾール<34μg →保留 ・合わせてACTH負荷試験を行う →Δコルチゾール>9μgは予後良好因子
→Δコルチゾール<9μgのnon responderの敗血症性ショック患者に対しては、ステロイド投与による28日死亡率低下の効果を認めた。
・ただし、これらの数値のもととなっているstudyはn数が少なく、信頼性に欠ける
→重症患者における副腎不全を検査で評価するのは困難と言わざるを得ない。
→(私見)コルチゾールが低下していることを確認するのには有用な可能性はあるが、確定的な情報は得られないものと考える。
c. 治療
・副腎クリーゼやCIRCIは早急な治療が必要であるため、その多くは疑った時点で治療が開始されるべきである。
・敗血症性ショックとの鑑別が難しいことがある。
→(私見)敗血症にCIRCIが合併することを考えると、実際には両者を明確に分けた治療戦略をとることは難しいと考える。
→ステロイド投与については、下記ADRENAL trialでも、(メインアウトカムは有意差がないものの)副次的な有用性が示されていることから、敗血症性ショックに対する輸液蘇生+ステロイド投与の治療戦略により、両疾患をカバーした初期対応がとられ得ると考える。

< ADRENAL trial >
Patient:人工呼吸を要し昇圧剤か血管作動薬が最低4時間使用された
18歳以上のSeptic shock
【Inclusion Criteria】
1. 18歳以上
2. 感染が証明されるか強く疑われる
3. 炎症のサインがある。以下の項目のうち2つ以上
・深部体温>38度もしくは<36度
・HR>90
・RR>20、PaCO2<32mmHgもしくは人工呼吸装着
・WBC>12000、<4000もしくは10%の好中球上昇
4. ランダム化時点で人工呼吸を使用(侵襲的人工呼吸、非侵襲的人工呼吸(CPAP, bilevel)のどちらか)
5. 収縮期血圧90mmHgもしくは平均動脈圧(MAP)60mmHg、もしくは臨床医が還流を保つために必要と定めたMAPを維持するのに昇圧剤もしくは血管作動薬が必要
6. ランダム化時点で4時間以上昇圧剤、血管作動薬を使用
【Intervention】
ソルコーテフ200mg/dayを連日持続投与
【Conclusion】
1. ハイドロコルチゾンは敗血症の90日死亡は減らさないことが真実として、副次評価であるショック離脱、ICU free days alive, MV期間短縮、輸血割合減少の4つのPositive Outcomeを期待して使用するか?しないか?
2. ハイドロコルチゾンで予後が改善する集団がいるという仮説を残すためハイドロコルチゾンを使用する、もしくは限定的に使用する。
http://www.kameda.com/pr/intensive_care_medicine/post_14.html
(追記)ソルコーテフ200mgは持続投与よりも50mg q6hrでの投与が優勢か?
Nejla Tilouche et al. Shock. 2019
<ステロイドカバー>
・循環動態に良い影響を及ぼすという明確なエビデンスは存在しない。
・投与の実際は下記

http://www.takanohara-ch.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/di201608.pdf
——————————————————————–
【14.甲状腺クリーゼ】
[参考]
・考えるERサムライプラクティス2014
・研修医当直御法度
・問題解決型救急初期診療
[まとめ]
・初発の心房細動は要注意!
→慢性疾患と勘違いして、鑑別・治療対象から外すと痛い目にあう
・心房細動を見たら甲状腺機能検査を行う。
・甲状腺クリーゼの急性期治療自体は、β遮断とソルコーテフという使い慣れた薬で行うので、そんなに怖くない。
→ただし急性循環不全の場合には、IABP/V-A ECMOの適応となりうる。
・ホルモン治療(チアマゾール、ヨード)は内科コンサルトで良いと考える。
(症例供覧:http://www.jcc.gr.jp/journal/backnumber/bk_jjc/pdf/J082-7.pdf)
[症例]
69歳女性
[CC]
心窩部痛
[Vital]
PR 156/min BP 120/80
RR 24/min BT 38.2
SpO2 96%(RA)
[PMH]
気管支喘息、子宮外妊娠で手術
[HPI]
午前3時から持続性心窩部痛が始まり、黄色嘔吐数回
排便は午後7字、排ガスあり
微熱と体重減少(10kg/1年)、著明な脱力
肺野清、心音不整
心窩部に圧痛あり、腹膜刺激症状なし
グル音減少、下腹部に手術痕あり
皮膚は発汗あり浸潤
[CQ0]
甲状腺クリーゼの定義及び診断基準はなにか
[A0]

http://www.japanthyroid.jp/doctor/img/crisis2.pdf
→感染、外傷、手術、ACS/PE、DKA、抜歯、妊娠高血圧、分娩が誘因となる。
[CQ1]
まず何をすべきか。
[A1]
ABCの評価及び、異常に対する介入
酸素投与、ルート確保、心電図モニター
その後12誘導心電図をとる
・Cの異常は、血圧とCRT2秒以上で素早く診断
・Dの評価をABCの安定が得られた後に行う。
→そうでないと、意識障害が過大評価される可能性がある
・生命を脅かす中枢神経障害のことを指し以下の徴候が出現する
・GCS8 (JCS30)以下
・GCS2点以上の急速な悪化
・瞳孔不同、片麻痺、cushing現象(呼吸抑制、血圧上昇、徐脈)
・切迫するDがあれば、primary survey終了時に頭部CTを撮影する。
・Eでは脱衣のうえ全身を観察。体温管理もこの際に評価。
[CQ2]
この症例で犯しそうなミスは何か
[A2]
心窩部痛+手術歴のみで病歴聴取をやめ、腸閉塞を疑って腹部XpおよびCT検査に向かう。
体重減少→大腸癌→腸閉塞というストーリーを組み立て、心房細動は既存の慢性疾患と思い込む。
→初発のAFは注意深く診察する必要がある。
→甲状腺クリーゼ、肺塞栓症、ACS、心筋炎・心内膜炎、僧帽弁弁膜症などで急性に発症する可能性あり。
[CQ3]
頻脈患者への対応は?
[A3]
症候性頻脈(血圧低下、胸痛、息苦しさ、めまい、意識低下など)がないかどうかを確認。
→症候性頻脈に対しては早急に同期下DCを行わなければならない。
→心房細動持続が48時間以内の除細動では、血栓塞栓症の危険性が低い傾向がある。
(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jstroke/31/2/31_2_79/_pdf/-char/ja)
(抗凝固開始の基準にもなるか)
→それ以上持続している場合には経食道心エコーが必要(むやみに救外でDCしない)
[CQ4]
心窩部痛の鑑別診断は?
[A4]
Red flag: AMI、大動脈解離、AAA、PE、急性膵炎など
その他:胆嚢炎・胆管炎、消化管潰瘍(穿孔)、虫垂炎の初期、SMA塞栓(AF合併例)、腸閉塞、急性胃粘膜障害・胃炎、たこつぼ型心筋症
[CQ5]
初発のAFのワークアップとは
[A5]
血算、電解質、心筋酵素、甲状腺、胸部Xp、心エコー、CHA2DS2
→日本人では女性であることが塞栓症のリスクとなっているとは言えないため、CHADSVASCよりもCHA2DS2を用いる。
①まずはACS、PEなどの心血管系疾患を否定
→胸痛・急性冠症候群score、TIMI
→肺塞栓のWells criteria、PERC
③その他
採血で貧血の進行や感染の存在がないかどうか確認する。
甲状腺機能亢進症の左室収縮はhyperkineticになり頻脈誘発性心筋症から心不全に至る。
[CQ6]
治療は?
[A6]
http://www.chugaiigaku.jp/upfile/browse/browse1493.pdf
β遮断→ステロイド→メチマゾール→ヨードの順に
①まずはβ1遮断などでrate contorolを行う
→急性期はランジオロールで良いでしょう(私見)
→甲状腺ホルモンの作用を減弱させ、精神症状などの症状にも効果を持つ
(当然、禁忌などに注意しつつ、適宜Ca拮抗などを使う)
ここまでを救急科で行えればよいだろう。
③メチマゾール(メルカゾール)
効果発現が遅い薬剤のため、逆にいえば超急性期で焦って投与開始しなくともよい。
④ヨード
甲状腺ホルモンの産生が低下していない状態で投与されると逆に甲状腺ホルモンを増加させてしまうため、急性期の投与なし
→必ず産生を低下させてから。
________________________________________
※治療レジメン
〇β遮断薬(厳密には保険適用なし)
・プロプラノロール
40-80mg q4h PO, 2mg q6h IV
・エスモロール
250-500μg/kgをローディング後、50~100μg/kg/minで持続常駐
・ランジオロール(オノアクト)
1~10μg/kg/minで調節
〇抗甲状腺薬
・プロピルチオウラシル(PTU)…甲状腺ホルモンの産生抑制
500-1000mgローディング→250mg q4h or 200-300mg q6h
・チアマゾール(MMI)…甲状腺ホルモンの産生抑制+T4からT3への変換抑制
60-120mg/日を4X~6X(IVorPO)
MMIの方が使いやすい(MMIを指示する報告もあるが、PTUvsMMIの明らかなエビデンスはない)
〇ヨード
・ヨウ化カリウム
250mg q6h PO
・複方ヨード(日本の保険適応なし)
〇リチウム
・炭酸リチウム(日本で保険適用なし)
300mg q6h (1mEq/Lを目安に適宜血中濃度測測定)
川良健二
その他の巻についてもこちらをご覧ください↓