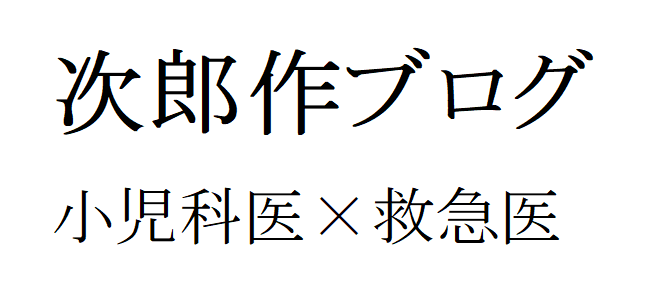「上京」
この甘美な響きは、今まで多くの田舎者を魅惑してきた。
「上京」にあこがれたり、時にさげすんだりする気持ちは、
都会で生まれ育った人には理解しかねるだろう。
そして、そんな僕も5年前、「上京」に無限の可能性を求め、
故郷「福井」を飛び出した若者の1人である。
上京したてのころは、右も左も分からなかった。
いや、正確には右や左は分かったが、
その代わりに、 米の炊き方、洗濯機の回し方、
そして、牛肉・豚肉・鶏肉の違い、が分からなかった。
僕は、類い稀な田舎者であった。
自分が強烈に訛っていることも分かっていなかった。
友達がバリバリの関西弁で話していることにも気付かなった。
「内ズック」が方言であることにも気付かずに、笑われた。
そんな時、周りにいたのが同じく「上京」したての寮生たちだった。
僕は、大学の寮に入ったのである。
そして、寮には地方出身の人が多かった。
みんな「上京」直後の、あの無垢な期待に充ち溢れていたように思う。
「志得ざれば再びこの地を踏まず」
かつて野口英世が上京の際に実家の柱に彫ったとされる言葉だが、
「上京」という行為の核心を突いた言葉のような気がしてならない。
では、いつから「上京」という言葉がこれほどの意味を持つようになったのか。
その答えを比較的近い時代に求めると、
大政奉還や廃藩置県により、東京の一極集中が進んだ明治維新前後と言えるだろう。
そして、そんな時代に、
今回紹介する本「坂の上の雲」の主人公である、3人の漢が生まれる。
日露戦争でコサック騎兵を破った秋山好古、
日本海海戦の参謀秋山真之、
そして、 文学の世界に巨大な足跡を遺した正岡子規、の3人である。
のちに各方面で日本を先導することになるこの3人は、
奇しくもほぼ同時期に四国松山に生を受け、
互いに密接なかかわりあいを持ちながら成長していく。
秋山好古と秋山真之は兄弟であるし、
秋山真之と正岡子規は同じ学校で学んだ学友である。
そして、3人とも例外なく「上京」する。
秋山好古のように、流れに身を任せた上京もあるが 、
秋山真之と正岡子規は若くして、東京へ行くことを熱望する。
若者が「上京」に言いようもない期待を求めるのは、
このころから変わりがないのかもしれない。
そんな3人の人生が、交差しながらも、次第に別々の道を歩んでいく・・・
今回紹介する一巻では、
3人が幼少期、少年期、を経て、それそれ青年になるまでの過程までが描かれている。
こういった書評は、八巻まで読んで、総じて論じるべきなのかもしれないが、
一巻からあまりに面白かったので、一巻だけで紹介させてもらった。
僕は本好きを自称するわりに小説が苦手で、いつも最後まで読めないことが多いのだが、
この本は久しぶりに一息で読破できた。
やはり、 「いい本というのは、頑張って読むものではなくて、本の方に最後まで読まされるものだ」という、
僕の考えはあながち間違っていないのかも知れない。
では、 最後は本文を引用し、この名著の雰囲気を感じてもらうのがよいだろう。
陸軍に所属している秋山好古、
その弟の秋山真之が、
「学者になる道から外れ、軍人になることを決める」場面を引用して、
この記事を終えようと思う。
「それなんじゃが。兄さん」
と、真之はいった。
「あしは、いまのまま大学予備門にいれば結局官吏か学者になりますぞな」
「なればよい」
「しかし第二等の官吏、第二等の学者ですぞ」
――ふむ?
と、好古は顔をあげ、それが癖で、唇だけで微笑した。
「なぜわかるのかね」
「わかります。兄さんの前ではあれですが、大学予備門は天下の秀才の巣窟です。まわりをながめてみれば、自分が何者であるかがわかってきます」
「何者かね」
「学問は、二流。学問をするに必要な根気が二流」
「根気が二流かね」
「おもしろかろうがおもしろくなかろうがとにかく堪え忍んで勉強してゆくという意味の根気です。学問にはそれが必要です。あしはどうも」
と、真之は自嘲した。
「要領がよすぎる」
中略
「なるほど、要領がいいのか」
好古は、真之の自己分析をまじめにきいてやった。
そのあと「学問には痴けの一念のようなねばりが必要だが、要領のいい者はそれができない」といった。が、かといって好古はこの弟のことを、単に要領のいい男とはみていない。思慮が深いくせに頭の回転が早いという、およそ相反する性能が同一人物のなかで同居している。そのうえ体の中をどう屈折してとびだしてくるのか、ふしぎな直感力があるのも知っていた。
(軍人にいい)
と、好古はおもった。
軍人とくに作戦家ほど才能を必要とする職業は、好古のみるところ、他にないとおもうのだが、あるいはこの真之にはそういう稀有な適性があるかもしれぬとおもった。
「淳、軍人になるか」
と、好古はいった。真之は、兄の手前いきおいよくうなずいた。が、よろこびは湧かなかった。軍人になることは、かれ自身がもっとも快適であるとおもっている大学予備門の生活をすてることであった。
子規の顔が、うかんだ。おもわず涙がにじんだ。