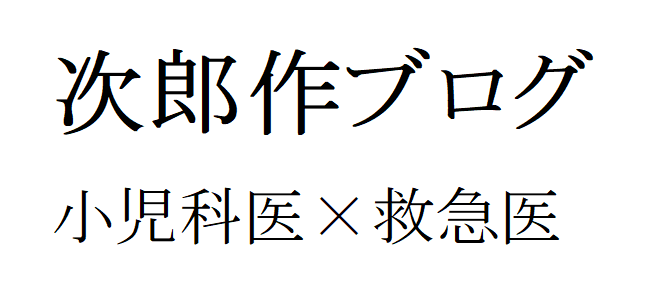物語の始まりはこちらから↓
第1話 エピローグ
——————————-
話は台湾の九分に戻るが、とにかく誰も加害者のいない惨めな被害者となったぼくは、わざわざ九份で探さなくても良い黒胡椒を、必死に探していた。
殊に、pepperとpaperの発音をし分けることが出来ず、何回もただのテッシュやトイレットペーパーを売りつけられそうになった。
この問題は、スペインやそれ以後南米大陸のスペイン語圏に突入するまで、永く続くこととなったのだが。
ともかく台湾では、ボラの卵巣を塩漬けにした珍味であるカラスミや、茉莉香のお茶こそ有名なお土産品であったが、黒胡椒などはどこの商店でも見つける事が出来ず、その日はトボトボと台北市内に帰ったのであった。
どうせ買うなら、日本で手に入らないような黒胡椒が良い。そう思い商店や市場を探してみるが、一つ目の黒胡椒ということも、あってうまく探すことが出来なかった。
結局はどこにでもありそうな、瓶詰めの黒胡椒をマーケットで買うことになり、次回こそは地産地消のものを、と意気込んだのであった。
そしてこの時、この黒胡椒探しというものが、奇妙にこの先の旅を演出し、ぼくの秘かな楽しみになるであろうということに、ぼくは気が付いた。
なんといっても、黒胡椒探しがうまくいかなかった瞬間に、「やはり台湾と云えど、外国にいるのだな」と強く実感したものだ。
韓国ではあまりの生活のしやすさに、なんと黒胡椒の買い付けを忘れてしまう、というオチはついているのだが。
魯肉飯や葱油餅、小龍包を堪能しているうちに、台湾でも最後の夜となった。
この夜ぼくは、初日に訪れた少し怪しげな地区へ、再び足を向けていた。林森北路である。
あてが無いという単純な理由で、初日に連れられて行ったバーへと吸い寄せられていった。
相変わらず日本語を上手に操る、艶美なママが出迎えてくれる。
「あら、この間あの人と一緒に来てた子ね。いらっしゃい」
「こんばんは。また来ちゃいました」
誰かに連れられて行った店に、初めて一人で行く時には、常に緊張が伴うものだ。
そんな緊張のせいか、こうしてはにかんだように、笑って挨拶するのがぼくの癖だった。
この時点でのぼくは、受け容れられているわけでも、拒絶されているわけでもなく、ここから店との関係性を築いていく必要があった。
店側としては、よっぽど態度の悪い客でもなければ、表立って出入り禁止のような拒絶行為を行うこともなく、一応は全ての客を受け容れているような素振りをとることが多いだろう。
だからこそ、真に人間として受け容れられているかどうかということを、注意深く洞察する必要があった。
私生活では決して会わない知人や、来た連絡を無視してしまうような鬱陶しい先輩でも、店に来てしまえばそれまでである。
人間としては受け容れられなくても、客としてはそんな彼を受け容れなければならず、そこが接客業の難しいところでもあり、かつ面白いところでもあった。店に一人で立っているような、小ぶりなところであれば、それは尚更である。
来るや否や、小難しい顔でそんなことを考えていたぼくに、ママは優しく話しかけてくれた。
「台湾にはいつまでいる予定なの?」
「今日がもう最後の夜なんです」
「それは残念ね…最後なんだから、楽しくしないとだめじゃない」
「いやぁ、そうなんですよね」
実はこの日、2月9日の夜を最終日として、2月10日にはタイへ向かうことになっていた。
日本を出た後、韓国、台湾、タイと移動することまでは事前に決まっていた。
冷静に考えてみれば、8ヶ月という時間で世界一周をするには、一箇所であまりのんびりはしていられなかった。
この時のぼくは「世界一周」という言葉の奴隷となり、あたかも世界一周が至上命題であるかのごとく、毎日あくせくと動いていたのだ。
「今夜はなにして遊ぶの?」
「今日はもうそろそろ帰って、明日の準備でもしますよ」
ぼくはあえて本心よりも、余計につまらなそうな表情を作っていた。
「それじゃつまらないじゃない。せっかく台湾最後の夜なんだから」
ママはそんなぼくのわざとらしい表情を、全て見透かしていながら、それを優しく包み込むような目で何かを考え、そして言った。
「なにも予定がないんだったら、私がドライブに連れて行ってあげるわ」
「え?!ママとドライブですか?」
「そうよ、最後の夜にドライブなんて素敵だと思わない?」
―驚いた、外国で夜にドライブだなんて、粋じゃないか
―いや、でも、そんな誘いにすぐ乗ってしまっていいのか。ママの考えていることが全然わからないぞ。海外ではそういう手口で騙されたりってよく聞くしな
先ほどまでは媚びた表情を向けていたママに、今度は猜疑心を含んだ目を向けている、小狡い男がそこにいた。
もちろんママは以前も今日も、優しくその場を楽しませてくれた。はっきりと言えば、彼女に対しては、正の感情を抱いていただろう。
しかしその個人的な感情も、いざ、「たった2回お店で会っただけの人物に、騙されないと言い切れるのか」と自問自答をした時には、弱々しく地面にへたり込むしかなくなっていた。
二つの矛盾する感情同士が、何度押し問答を繰り返しても決着が付かず、あたかも自分で自分を傍観しているような気持ちだったが、その状況をあっけなく終わらせてくれたのは、日本人特有の、「断れない性格」だった。
誘ってくれた人を目の前にして、やはりその人の好意を(正確にはこの時点でそれが好意かどうかはわからなかったが)無下にすることは出来なかった。
―こうして海外で日本人が騙されていくんだな
半ば自棄になりながら、ぼくはママの誘いに乗っていた。
続きはこちらから↓
7話 今夜ひみつのバーで 第1節 -台湾
Facebookページのイイね!お願いします!
![]()
にほんブログ村
応援or順位確認お願いします。