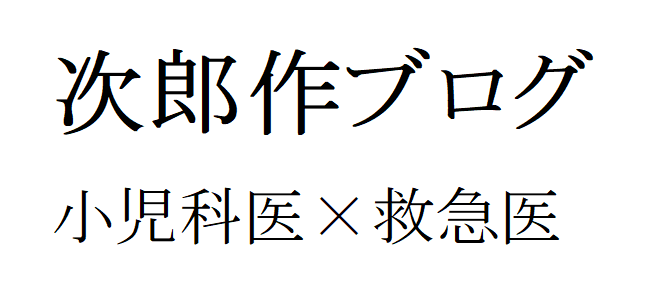物語の始まりはこちらから↓
第1話 エピローグ
——————————-
雨が降りしきり、寒く侘しい場所だった。
誰か友人や恋人と行けば、感受の仕方も変わったのだろう。しかしそこにあったのは、寒々しく拒絶されているとすら感じさせる場所であった。
暗がりを灯す赤いひかり、そしてそれに照らされる、狭い小道や商店は、ともすると幻想的に映るはずだが、この時のぼくにはどこか黄泉の世界を彷徨っているような、うしろ暗い印象を与えたのだった。
周りの観光客から蔑まれているような、自虐的な妄想が脳をかすめ、ただひたすら足早にその場をやり過ごそうという気持ちで観光していた。
気がつくとぼくはとある目的を持って、九份の商店という商店を歩いて回っていた。
その目的を持つに至った経緯は、この旅行の出発前、日本でのある会話に遡る。
同年1月の中旬、日頃から仲の良い付き合いをしていたある夫妻の家で、ぼくは晩飯とそれから、翌朝飯をご馳走になっていた。
急だったにもかかわらず、その晩の寝床まで用意してくれたのだった。
それから程なくして、その夫妻と会う機会があり、世界旅行に行くことを告げると、奥さんは興味を持って話を聞いてくれた。
行ったことのある国、行きたい国、あそこの景色が壮大だなどの話をしているうちに、どこの国の料理が美味しいかという話題になった。
日頃から色々な食材を使って料理をするのが得意な彼女にとっては、気になる事だったのだろう。そして話題は世界の調味料ということにまで及び、そこで黒胡椒の話が出たのだった。
気が付くと、ぼくは世界中で黒胡椒を買ってきて、それをお土産にする約束をしていた。
幾つの国に訪れるのかということはおろか、どこに行くのかもまだ決めていなかったぼくにとって、その約束をするのは簡単なことでは無かったはずだ。
きっとこの時ぼくは、「人から喜ばれる」ということに飢えていたのだろう。
「一宿一飯の恩義」という言葉があるように、もちろんその日についての恩は感じていた。飯と寝床というもの以上に、何か暖かいものが身に沁みたのだ。
しかし、黒胡椒の件を引き受けたのは、それだけの理由だったのか、と今になって思う。
思い返せばその時のぼくは、ささくれだった指先から滲み出る血のように、地味に長く自分を痛めつける、自責の念に苦しめられていたのだ。
現役で入学した大学は、三年から四年に進もうという春に中退していた。
その後の一年間を受験勉強に捧げ、翌春には今の医学部に再入学することが出来たが、ようやく入った医学部を、今回さらに休学して、しかも親からの借金で世界旅行に行こうというのだから、きっとぼくはどうかしている。
そんな親不孝は許されない。そのことは26歳にして、「親に甘えた」としか表現しようのない事実であった。
奥さんと会話をしながら、黒胡椒の話題とそんな回想が、お互いを見つめ合っていた。
結局のところ、そんな自分の痛みを少しでも和らげるために、人から感謝されるなにかがしたかったのだろう。
恩返しということにおいては、決して主体的ではない動機がぼくを動かし、気が付くと約束をしていたのだった。
Facebookページのイイね!お願いします!
![]()
にほんブログ村
応援or順位確認お願いします。